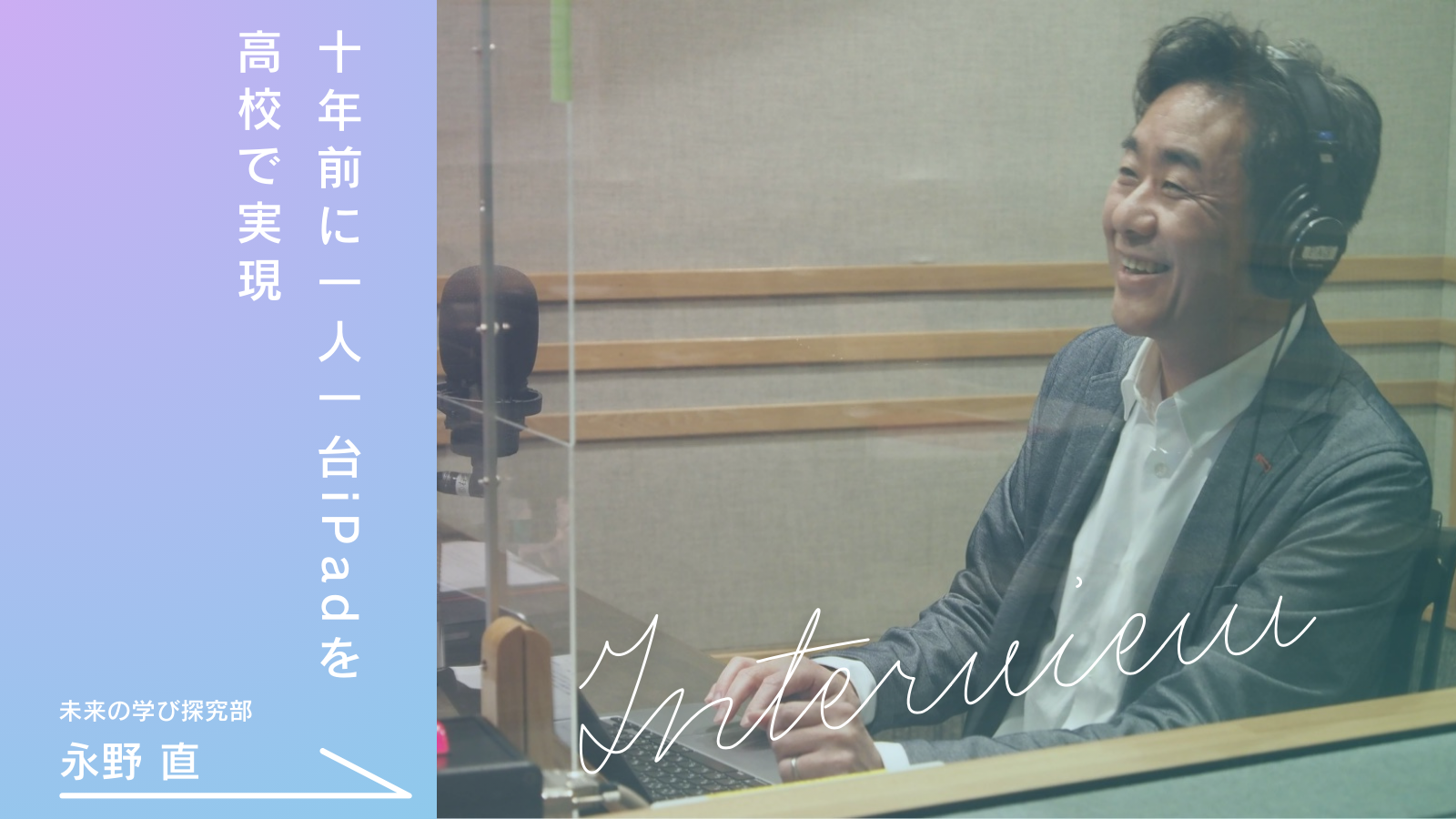情報教育の新時代を切り開く元高校教師の挑戦
こんにちは、みんなのコードの永野です。私は、みんなのコードで主に高校の情報科の支援をしており、先生方に向けた研修などを担当しています。
今回は、私のこれまでの歩みや、これから取り組みたいことなどについて話したいと思います。
幼少期はゲームに没頭
私の幼少期はビデオゲームが出始めたころで、インベーダーゲームなどに熱中し、とにかくゲームが大好きでした。親は高校の化学の教員で、たまにゲームセンターに連れて行ってくれましたが、ファミコンなどの家庭用ゲーム機は買ってもらえませんでした。ゲーム機を持っている友達がとても羨ましかったのを覚えています。
小学校高学年の頃、家の近所に住んでいた知り合いの大学生がコンピュータを持っているのを知り、触らせてもらいに頻繁に遊びに行っていました。当時のコンピュータの雑誌には、ゲームなどのプログラムが載っており、ゲームがやりたい一心で、意味もわからず何ページにも渡るプログラムコードを打ち込みました。それが初めてのコンピュータとの出会いです。
その頃、初めてBASICという言語でプログラムを作ったのですが、どうしてできたのか今思うと不思議です。教えてもらったわけでもなく、いつの間にかできてしまったのですから、好きという情熱はすごいものです。その後中学生になると部活で忙しくなってしまい、コンピュータから遠のいてしまいました。ただ、子どもの頃からデジタル的なものに好奇心旺盛だった性格は、大人になった今でも変わっていないなと感じています。
高校教員として情報の授業に関わり始める
さっきも少し書きましたが、私の父は高校の教員で、幼少期の頃から教師になって欲しいと言われていましたし、自分も教師になるんだなと漠然と感じていました。今思えば、当時は教員になる強い使命感のようなものはまだ持っていなかったのかもしれません。
採用時は地歴科の教員として、地理を担当していました。世界各地の食べ物や文化の違いに興味があり、学生時代から地理が一番好きでした。
最初の赴任先だった高校は、小中学校の勉強でつまずいてしまい、やる気を失ってしまった生徒が多い学校でした。授業をしていても漫画を読んでいるか、寝ているか、時には教室から逃げ出してしまう生徒もいました。当時は、どうしたら生徒たちが授業に参加してくれるのか、何かこの子たちにできることはないかと、その状況に悩む日々でした。
そこで、当時学校でも使われるようになり始めた、インターネットを授業に用いることにしてみました。生徒自身で世界各国のことを調べたり、資料を作って発表する授業など、教員の説明よりも、生徒の活動を重視した授業をすることで、生徒たちが少しずつ授業に参加するようになってきたのです。こういった経験を通して、授業とは先生がただ一方的に話すのではなく、生徒の学習活動こそが大切なのだと気付きました。
そこから自分自身のコンピュータやインターネットへの興味がますます高まり、授業でコンピュータを用いることを続けました。例えば、地形の等高線の説明に立体的なコンピュータグラフィックスを取り入れたこともあります。そういった活動は文部科学省のICT活用事例集にも取り上げられました。
※http://www2.japet.or.jp/itnavi/jirei/ITN51001.html
http://www2.japet.or.jp/itnavi/chirashi.pdf
そんな矢先、高等学校に「情報」という新教科ができるらしいと聞きました。私は「これからの時代、『情報』を扱う力が重要になる!ぜひ情報の授業を担当したい」と感じ、情報の免許を取得することにしました。
子供たちに何を学んで欲しいのか、教員として強い使命感を持ったのはこの時からでした。教員として採用され、10年近く経った頃にようやく本当の意味で「教員」になれたのだと思います。
その後はずっと情報科の授業を担当してきました。コンピュータについては独学ですが、必死に自ら学びながら授業をしていたなと、当時を振り返ると感じます。
授業を担当しながら情報への興味はますます高まり、より情報教育について研鑽を深めようと、2年間学校現場を離れて大学院で学びました。マルチタッチパネルデバイスの教育活用を修士研究のテーマとし、これが次の学校での取り組みにつながることになります。
大学院修了後の2010年に「10年先の普通教室」というビジョンのもと、日本の公立高校として初めてタブレット端末を生徒が自己所有する学科を計画、翌年に実現させました。はじめのうちは「タブレット端末なんて高校生に必要ない」などの批判も多かったのですが、次第に全国の学校から視察などが来るようになっていきました。あれから10年が経って、本当に児童生徒の1人1台環境が「普通の教室」となったことは、とても感慨深く感じています。
教員からの新しい挑戦の場所がみんなのコード
小学校でもプログラミングが始まると話題になっていた2018年頃には、総合教育センターに研究指導主事として異動になりました。教育センターでは、情報教育に関する教員研修の企画・運営をしていました。これから始まるプログラミング教育のために、小中高の先生方のサポートをしなければと感じていましたが、当時はプログラミング教育のノウハウを持っている人はほとんどいなかったのです。
そんな時、みんなのコードが小学校プログラミングの研修に協力してくれると聞き、研修講師として竹谷が来てくれました。これがみんなのコードとの関係の始まりです。県でのプログラミング教育のイベントなども一緒に手伝ってもらいました。
その後、私はセンターを離れ学校に戻る時期になりました。自分が取り組んできた情報教育にこれからも携わっていきたいという気持ちと、管理職として自分がこれからしていくべき仕事の違いを考え、悩む日々でした。そんな時、みんなのコード代表の利根川から「全国の先生方と関わりながら日本の情報教育を盛り上げていく仕事をしませんか?」と熱意をもって誘われました。
全国各地のまだ知らない先生方と出会いながら、情報教育の世界をアップデートしていく仕事はとてもやりがいのある面白そうな仕事だと感じました。妻も、自分の好きなことをやったらいいんじゃないと賛成してくれ、みんなのコードに加わることとなりました。あの時、新しいチャレンジに背中を押してくれた妻には本当に感謝しています。
アラムコSTEAMチャレンジという新たな挑戦に向けて
みんなのコードに入ってからは、高校情報の授業のあり方などについて、研修を行っています。他の企業でも、プログラミング言語やプログラミングスキルを高めるための研修をやっているところはたくさんあります。私は、生徒たちが情報教育の面白さを感じながら学ぶこと、そしていかに教員がそのサポートをするかを重視しています。
黙って座っている生徒に向かって、先生が一方的に教えても響かないということは、過去に私自身が経験しています。生徒に1から10まで教えるのではなく、主体的に考え、活動したり体験したりしながらプログラミングを学ぶことが大切だと思っています。子どもたち自身がなぜ学ぶのか納得し、面白いと感じられるような情報教育を実現していきたいと思っています。
そんな意味でも、今回私が取り組むことになったアラムコSTEAMチャレンジは、とてもいい機会です。小学校の図画工作や、中学校の技術・家庭のような、ものづくりを通して学ぶ授業は工業科を除いて高校ではとても少ないのが現状です。子どもたちが「つくりながら、実感を持って学ぶ」ことは、自分が今まで大切にしてきた考えそのものです。
体験と実感を大切にしながら子どもたちの学びを育てていきたい、という現場の先生たちと一緒に、アラムコSTEAMチャレンジに取り組んでいきたいと思っています。
今回ご支援いただいたアラムコ・アジア・ジャパン株式会社は、サウジアラビアの総合エネルギー・化学企業アラムコの日本現地法人です。
▶︎アラムコ・アジア・ジャパン:Where Energy is Opportunity | アラムコ・ジャパン ( https://japan.aramco.com/ )
▶︎アラムコ:Where energy is opportunity | Aramco
( aramco.com )