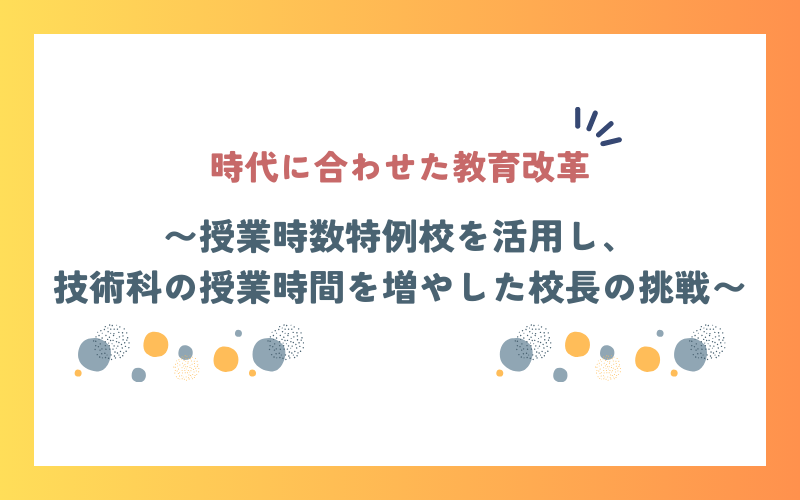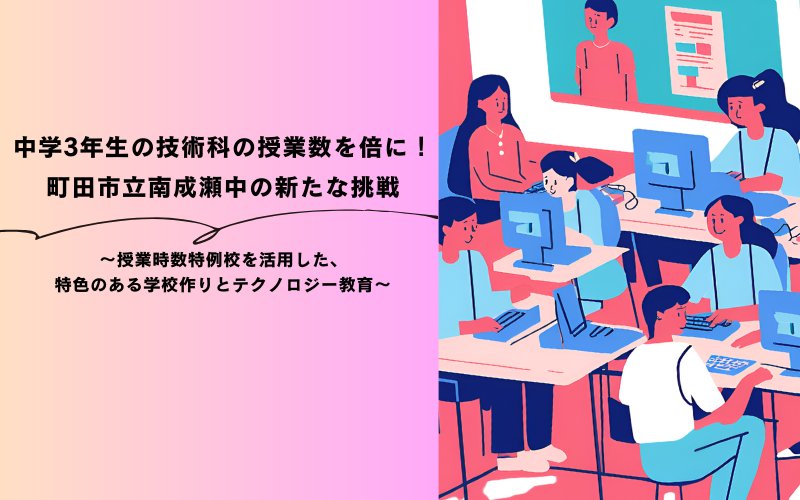みなさん、こんにちは!みんなのコードで中学校の担当をしている千石です。普段は、中学校の技術科向けの教材やカリキュラム開発、先生方への研修を行っています。実は私自身、東京都内の中学校で技術・家庭科(技術分野)の教員として11年間勤めていました。現場の経験を活かして、教育現場の変化や新しい取り組みをサポートしています。
前回の記事では、授業時数特例校制度を使って技術科の授業時数を増やす実践を行っている、町田市立南成瀬中学校の笠松先生のインタビューをご紹介しました。今回は、授業時数特例校の申請を決めた杉浦校長先生にお話を伺います。
南成瀬中は、学校独自の取り組みとして情報教育に力を入れたいと考えていたところ、みんなのコードの「教育課程・授業時数特例校制度で取り組む特色ある情報・テクノロジー教育事例について」を知り、2024年度から中学校3年生の技術科の時数を17.5時間から35時間に増やす実践を行なっています。
*授業時数特例校制度とは
授業時数特例校制度とは、通常の学校よりも柔軟な授業時間数を設定できる制度です。この制度は各学校単位で申請することができ、地域の特性や生徒のニーズに応じた教育を提供できるようにすることを目的としています。具体的には、学習指導要領で定められた授業時間数を基準にしつつ、学校が独自に設定した教育目標に合わせて授業時間を調整することが可能です。
話し手:町田市立南成瀬中学校 杉浦元一校長(肩書きは2024年インタビュー当時)
聞き手:みんなのコード 講師・研究開発 千石一朗
教育課程上の課題感
千石:授業時数特例校の申請において、技術科の授業時数を増やす判断をされた理由を伺ってもよろしいでしょうか?
杉浦校長:これだけ世の中の変化が激しい現代で、最先端のテクノロジーに触れる教科であり、情報活用能力能力育成の中核であるはずの技術科の時間数が一番少ないのはおかしいと思っていました。
また、実技系の教科にもっと力を入れて行きたいと感じています。
千石:それはみんなのコードが考える「小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデル案」とも一致するお考えですね。具体的にはどのような点が課題でしたか?
杉浦校長:現在の学習指導要領では、中学3年生の技術が0.5時間/週、家庭科が0.5時間/週というのは、以前から課題だと感じていました。2週間に1回の授業では何も進められません。技術科も家庭科も同じです。
私が中学生だった頃は、3年生の技術では、週3時間ありました。そうした時代を考えると、今の授業時数では積み重ねができず、できることが非常に少ないですね。
千石:技術科の授業時数を増やしたことによる影響や、学校運営上、発生した問題などについても教えていただけますか?
杉浦校長:大きな混乱はありませんでした。
ただ、時間割の調整に少し手間がかかりました。週ごとに異なる教科から時間を割り当てる必要があり、時間割担当の教員にとっては負担が増えたと思います。それでも、全体として見れば、学校経営上大きく前進したと感じています。
むしろ今回の取り組みを経て、技術科の時数はさらに増やしたいという気持ちになりました。
授業時数特例校の申請について
千石:ここからは、授業時数特例校について伺ってもいいですか?
授業時数特例校の申請は前年度の12月に締め切られます。このスケジュールだと先生方の異動も決まっておらず、管理職の先生方が特色のあるカリキュラムを作りたいと思っても、行動しづらいように感じています。
授業時数特例校の手続きについて、校長先生の立場として「もっとこうしてくれると制度を利用しやすくなる」という点や、制度面での希望はありますか?
杉浦校長:教育課程を年度末に組む段階で、人事が固まっていないのは現状では仕方ありません。しかし、人事が早く固まったとしても、多くの管理職がこの制度を積極的に活用するかというと、そうではないと思います。
学校にいる教職員が、実現したい教育を形にするためには、管理職の熱意の方が重要だと思います。明確なビジョンがなければ、制度があっても活用されないでしょう。
千石:なるほど、制度上のハードルを下げることよりも、管理職の先生方の熱意やリーダーシップの方が大切と言うことですね。
生徒や保護者からの反応について
千石:技術科の時数を増やした取り組みで、生徒の反応はいかがでしたか?
杉浦校長:プログラミングの授業は生徒たちに非常に好評です。難しさを感じる部分もあるようですが、自分から進んでやりたくなるという声が多いです。やはり彼・彼女らもこれから社会に出て生きていく中で、この学びは絶対に必要になる、ということを肌で感じているのだと思います。
千石:実際に授業を受けたことで、生徒への変化や影響はありましたか?
杉浦校長:具体的な進路に結びついているケースもあります。今年は女子生徒が技術系の分野に進みたいと希望するケースがあり、これは授業の影響が大きいのではと感じています。
千石:保護者の方々からの声は何かありましたでしょうか?
杉浦校長:さまざまな意見がありました。例えば、「新しい選択肢が広がることで、子どもの可能性を引き出せるのは良い」という声がありました。特に、まだ自分の興味のある分野が定まっていない時期に、多様な学びの機会が提供されることに、期待感を持っている保護者が多いようです。
千石:授業を受けた生徒の様子に関する保護者の方々の声はありましたか?
杉浦校長:「楽しかった!」と家庭でも嬉しそうに話していた、という声が多かったですね。また、「新しいことへの興味やモチベーションが芽生えているように感じる」という保護者の声もありました。生徒が自分の意志で学びに向かう姿勢を持つようになったことは、大きな成果の一つだと考えています。
千石:今回の学校の新しい取り組みについて、保護者の方々はどのように評価していますか?
杉浦校長:「学校が先進的な教育を取り入れる姿勢は良い」という意見が多くありました。また、「こうした取り組みが広がることで、子どもの学びの可能性がさらに増えると期待している」という声もありましたね。義務教育の中でこうした柔軟な学びの場が提供されることは、保護者にとっても価値があると感じてもらえたようです。
千石:生成AIを活用した授業も行いましたが、そのことについての意見はありましたか?
杉浦校長:はい。「家庭でもChatGPTを活用しているため、技術の可能性や注意点を学校で理解できているのはありがたい」という声がありました。AIの基本的な考え方や使い方を学校で学ぶことの重要性についても、多くの保護者が共感していましたね。
学校の特色を出してくために
千石:授業時数特例校の制度を他の学校にも勧めるとしたら、どのようにアプローチすればよいとお考えですか?
杉浦校長:この制度は、学校の特色を打ち出すのに非常に有効です。これまで学校の特色というと、総合的な学習の時間であったり、学校行事であったり、部活動であったり…そういったところでしか差別化できませんでした。この制度を活用すれば、教育課程の中身で特色を出すことができます。
また書類作成の負担も少なく、継続申請が簡単なのも利点です。他の学校でもぜひ活用して特色のあるカリキュラムを打ち出してもらいたいですね。
参考:教育課程特例校制度・授業時数特例校制度https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokureikou/index.htm
インタビューを終えて
インタビューを通じて、技術科の授業時数の増加が生徒の学びに与える影響の大きさを実感しました。生徒たちはプログラミングをはじめとする、技術科の学習に積極的に取り組み、進路選択にも好影響を受けています。
また、保護者からも「新しい学びの機会が子どもの可能性を広げる」といった前向きな意見が多く寄せられました。不確実な時代を生き抜くために必要な学びに対する関心が高まっていることを感じます。こうした保護者の声を受け、私たちが提言する「小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデル案」において、中学校技術科の授業時数増加に関する実践に肯定的な意見をいただき、大きな励みになりました。
そして、先日の文部科学省が発表した「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」(諮問)においても、学校が柔軟な教育課程を編成できるようにする方針が示されています。授業時数特例校のような既にある制度を活用することでも、各学校が時代に即した特色あるカリキュラムを構築できる可能性が広がります。今回の取り組みが一例となり、より多くの学校で柔軟な教育課程が実現されることを期待しています。