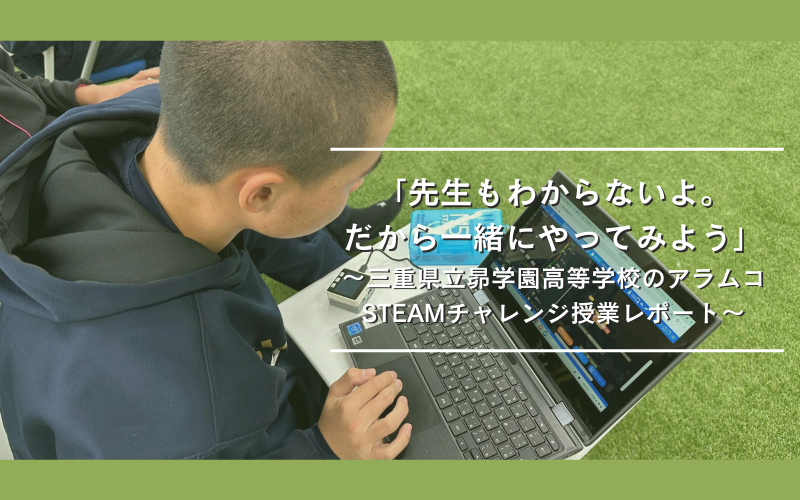こんにちは。みんなのコードの永野です。主に高等学校のプログラミング教育の教員研修などを担当しています。
今年の7月より、アラムコ・アジア・ジャパン株式会社様の助成のもと実施しているアラムコSTEAMチャレンジ(以下、アラムコSC)について、既にいくつかの記事でご紹介していますが、先日採択校である三重県立昴学園高等学校の授業を見学させていただきましたので、その様子をレポートします。
昴学園高等学校の「大台探究」
三重県立昴学園高等学校は、三重県多気郡大台町にある県立学校では全国唯一の全寮制の総合学科高等学校です。
授業は普通科や専門学科とは異なる柔軟なカリキュラムが特徴で、国際交流やスポーツ、美術工芸、環境技術などのコースがあり、生徒の多様な学びの実現に取り組まれています。
今回見学させていただいた「大台探究」は、2年次の選択科目で、授業時間は1コマ90分です。大台町はユネスコの生物圏保護区(ユネスコエコパーク)に指定されており、「大台探究」ではこの自然豊かな大台町をフィールドとして、自ら課題を見つけ調査・研究を進め、解決策を提案・実践する探究学習が行われています。生徒たちは学校内での学びにとどまらず、地元企業の人が特別講師となったり、地域住民の方々にインタビュー調査を行ったりするなど、社会と深く結びついた問題解決に取り組んでいるそうです。
今年度の「大台探究」は、2年生の4名の生徒が履修しています。教室は壁の3面がホワイトボードとなっていて、アクティブラーニングルームといった感じです。床は人工芝となっていて、先生も生徒もみんな靴を脱いで授業に参加し、のびのびと学べる教室となっていました。このような教室環境、少人数、長時間の時間割も、生徒一人ひとりの個性や適性に応じた学びを促しているように感じました。
先生が「教えない」学びとは
アラムコSTEAMチャレンジで昴学園高校が選択したSTEAM教材は「M5GO IoTスターターキット」です。M5Stackは液晶ディスプレイを備えた小型のマイコンモジュールで、温度や湿度などを計測する外部モジュールも接続できるので、アイデア次第で「大台探究」に有効に使っていただけそうでした。ちなみに、生徒たちは見学した日に授業で初めて「M5Stack」に触れたとのことです。
授業が始まって、まず「大台探究」の担当教諭である山﨑恵介先生が生徒に伝えたことは、「先生は教えないよ」ということでした。
「まずは色々いじって、どんなことができるか自分たちで見つけてみよう」と続けます。
「教えない授業」というのは最近よく耳にする言葉です。しかし実際には「先生の解説動画」を生徒がそれぞれのタイミングで視聴することであったり、ワークシートで学習の流れが細かく指定されていたりすることも多くあります。つまり、「先生が授業中に解説しない」だけで、本質的には「先生が教えている」ような授業も多く見かけます。
しかし、山﨑先生の授業は本当に「教えない」のです。
初めてみる「M5Stack」を、プログラムによって
・画面を赤や黄色の色に変えてみる
・音を鳴らしてみる
・何か「文字」を画面に表示してみる
という課題だけ決めて「じゃあさっそくやってみよう!」ということで実習がスタートしました。
創造的な教育の本質「ティンカリング」
生徒たちが初めて目にしたのは以下のような画面です。
ブロックプログラミングに慣れた人ならなんとなくわかるかもしれませんが、初めての人にとっては、何をどうすれば良いのかさっぱりわからないと思います。
生徒さんたちは「これどうしたらいいんだろう」と戸惑っていましたが、それに対して山﨑先生は「先生もわからないんだよ。だから一緒にいろいろいじってみよう」と返していました。山﨑先生はさらっと言っていましたが、「教える」ことに慣れている教員にとって、このように言える人はそう多くありません。
見学していた私たちも、先生の「授業のねらい」に反しないよう、「教えない」つもりで授業に参加しました。しかし、授業を見学していると「うーん」と頭を抱える生徒たちの姿を目の前にし、「さすがにこの部分だけでも説明してあげないと進まないのでは?」という考えが頭をよぎりました。
むずむず、辛抱しながら数分していると、「あ!!できた!!」と1人の生徒が声を上げました。「えっ、どうやったの?」「本当だ!すげぇ」などという言葉と共に、生徒たちのやりとりがはじまり、先生も「えっ、できたの?すごいなぁ、まだ先生できてないぞ」などとにこやかに返しています。
これはまさに「ティンカリング」です。「ティンカリング」とは直訳すると「いじくりまわす」という意味で、試行錯誤しながら手を動かし、創造的に問題を解決する学習方法です。特に、ものづくりやプログラミング、電子工作などの学習の際に使われる手法です。
幼い子供はおもちゃを与えられると、大人の解説など待たずにすぐに触り始めます。興味の赴くままに、色々と試し、自ら考えながら学んでいきます。ティンカリングは、「とりあえずやってみる」という学習者の意思を尊重する学び方であり、創造的な教育の本質であり、主体的に自由に手を動かしながら試行錯誤し、失敗を歓迎し、プロセス自体を楽しみます。
これは、素晴らしい手法ではあるのですが、実際の授業で実践するにはなかなか難しいものです。まず、指導者である教師にとって「我慢」が必要です。「教える立場」であった教師が、生徒があれこれ悩む場面をみると、つい「こうすればできるよ」としてしまいがちです。
また、生徒にも「どうせ、いつか先生が教えてくれる」という意識があるとうまく進みません。しかし、「大台探究」を履修している生徒たちからは、教員頼みのような姿勢が全く見られませんでした。常日頃から、生徒たちの主体的な学びが根付いていることが伺えました。
このような学びには「教える授業」より時間がかかるのは確かです。しかし、このように生徒が主体的に取り組み、充実しながらも「余白」をもって取り組む学びこそが、STEAM教育の本質なのかもしれません。
授業では、ほとんどの課題を生徒たち自身でクリアしました。そこで、山﨑先生から「今日見学にきているみんなのコードの永野さん、千石さんから、生徒たちにぜひ追加の課題を出してくれませんか?」という依頼がありました。
そこで、わたしたちからは
大台探究として
・大台町の自然環境の調査などにも活用できること
・今日のこれまでの学習を発展させて実現できること
の2つを考えてもらうため、「センサを接続して、画面に現在の気温を表示させること」を課題として出しました。
生徒たちは、センサの接続も初めてでしたが、やはりこちらからはやり方を教えませんでした。
失敗しながらも、生徒同士、そして先生も一緒に楽しげに対話しながら、着実に改善を続け、課題を達成することができていました。
授業の最後には、この後に続く「大台探究」にむけてM5Stackを使って各自どんな活用ができるか、生徒たちが想像しながら授業が終わりました。
授業を終えて
授業後、山﨑先生が、
「探究が調べ学習で終わってしまったらもったいない」
「生徒にもっと面白いことをやってもらいたい」
「自分は結果が決まりきったことは面白いと思えないし、わからないことだからこそ楽しい」
とおっしゃっていたのが印象的でした。
プログラミングの授業として、もっと高度なことをやっている高校はいくらでもあるでしょう。
しかし、「一体なんのためにやっているのだろうか」と思っている生徒は少なくないのかもしれません。昴学園高校の生徒たちは、少なくとも「やらされている」という意識は全くないように見えました。彼らは、これからも学びを純粋に楽しみ、そして自分が取り組みたいと思うテーマに従って、創造的に探究を進めていくのだろうなと実感しました。
山﨑先生は、「大台探究」の学びにSTEAMの視点を取り入れてバージョンアップするために、アラムコSTEAMチャレンジに応募されたとのことでした。
採択時、山﨑先生は「探究のテーマに「大台町の自然」が関連していたとしても、これまで生徒は、「宮川の水はきれい」といった感覚的な認識にとどまっていた」とおっしゃっていました。
続けて、「このアラムコSTEAMチャレンジを通して、その感覚的な『きれいさ』とは何を指しているのか。例えば、センサやIoT、プログラミングやデータサイエンスの視点を取り入れることで、生徒たちの疑問がより明確になり、探究がさらに深まるものになるのではないか」とお話しされていました。
みんなのコードは、教育の「地域格差」についても取り組んでいます。アラムコSTEAMチャレンジでは、STEAM教材が不足している地方部への教材提供が目的の一つとなっていますが、地域格差の是正とは単に「地方の学習環境を都市部に合わせれば良い」ということではないはずです。地域の環境をうまく活かしながら、テクノロジーによってその特徴をより理解しやすくしたり、魅力を発信しやすくすることで、地域の教育が魅力的になるのではないでしょうか。
来年度も昴学園高校「大台探究」でのアラムコSTEAMチャレンジは続きます。これからも、生徒たちのより楽しい、より深まりのある課題解決のために、本事業が少しでも役立つことを期待しています。
今回ご支援いただいたアラムコ・アジア・ジャパン株式会社は、サウジアラビアの総合エネルギー・化学企業アラムコの日本法人です。
▶︎アラムコ・アジア・ジャパン:Where Energy is Opportunity | アラムコ・ジャパン ( https://japan.aramco.com/ )
▶︎アラムコ:Where energy is opportunity | Aramco
( aramco.com )