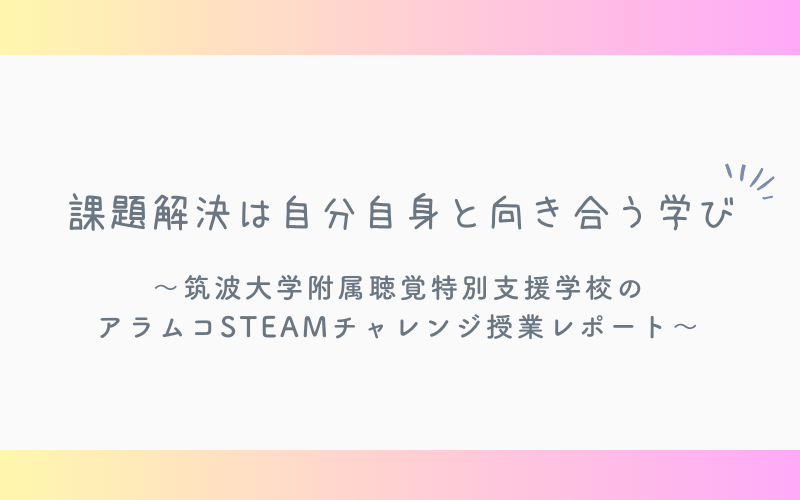こんにちは、みんなのコード パートナー部(ファンドレイジング担当)の花田です。
みんなのコードは、2024年6月より、アラムコ・アジア・ジャパン株式会社様の助成のもと、中学・高校のSTEAM学習における教材不足解消を支援する「アラムコSTEAMチャレンジ」に取り組んでいます。私は、「アラムコSTEAMチャレンジ」の事務局を担当しています。
先日、採択校である筑波大学附属聴覚特別支援学校の授業を見学させていただきました。今回は、その様子をレポートします。
筑波大学附属聴覚特別支援学校は、日本で唯一の国立大学附属の聴覚特別支援学校で、聴覚に障がいのある児童・生徒が学んでいます。
私たちの“無意識の偏見”の存在
授業見学のレポートに入る前に、今回の見学を通じて私たち自身に生じた意識の変化についてお話しさせてください。
見学してから気づいたことですが、見学する前の私たちは、「STEAM学習を行う上で、生徒たちに対してどんな「特別」な「支援」が行われているのだろうか」と、無意識に考えていました。
しかし、実際に授業を見学させていただき、その印象は大きく変わりました。課題解決学習についても生徒たちに特別に配慮したテーマが設定されているわけでもありませんでした。
私たちは勝手な思い込みにとらわれていたのです。
「普通の授業だった」と感じること自体が、わたしたちが「特別支援学校」についてバイアスを持っていた証拠なのかもしれません。そんな気づきを得ることで、私たち自身が持っていた認識の課題とも向き合う機会となりました。
授業について
今回は、計測・制御システムの仕組みを学びながら、プログラミングによる課題解決に取り組む技術科の授業を見学しました。生徒たちが身近な問題を発見し、テクノロジーを活用して解決策を考える内容です。
この授業では、タコラッチという教材を用い、センサによる入力とアクチュエータによる出力を組み合わせたプログラムを作成しながら、実践的に学んでいきます。生徒たちはどのように学び、課題を解決しようとしていたのでしょうか。
授業概要
- 授業目標: 計測・制御システムについて理解する
- 単元と授業内容
- D情報の技術
- D(3) 計測と制御のプログラミングによる問題解決
- 学習内容:タコラッチを活用し、センサによる入力とアクチュエータによる出力を組み合わせた課題解決を考えながらプログラミングに取り組む。
- 授業時間数
- 全3時間(みんなのコードは2校時目、3校時目を見学)
- 対象学年
- 中学3年生
第2回目の授業:身近な問題から考える「解決したい課題」
みんなのコードが見学した、2回目の授業では、生徒たちが2-3人のグループに分かれ、タコラッチに付属する課題解決カードを用いながら身の回りの課題解決方法を考えていました。
そして、タコラッチを使い、どう課題を解決していくかをグループでアイデアを出していました。まず、課題カードから解決したい課題を選択していきます。次に解決に必要な、計測と制御のカードを一枚ずつ選択します。カードの裏にはそれぞれの課題に対するプログラム例が書いてあるので、これを参考にScratchでプログラミングをしていきました。
以下のようなアイデアをもとに、生徒たちは、課題解決のアイデアについて、クラスメートと積極的にコミュニケーションしながら、試行錯誤を重ねていました。
- 寝たきりの高齢者がヘルプサインを出した時に家族に伝える仕組み
- 不審者が侵入した際に警告するシステム
- 朝起きられない問題を解決するために、ベッドごと起き上がる仕組み
課題の選択までは、スムーズに進むグループが多かったように思いました。次の工程であるプログラミングには、少し苦戦する姿もありましたが、課題解決カードの裏面のヒントや、先生からのアドバイスを受け、粘り強くプログラミングに取り組んでいました。
次第に、それぞれが自分の解決したい課題に対して、どんな機能を使えば実現できるか、どんなプログラムを作ればいいか、と活動が具体化していきました。
うまくいかないときになんでだろうと模索する姿や、自分たちのプログラムが思い通りに作動した時、思わず歓声をあげ、互いにハイタッチを交わして喜びを分かち合っている姿が印象的でした。
試行錯誤しながらも達成感に溢れている姿をみて、パソコン上だけではなくSTEAM教材を通して実践的な学びができる、今回のプログラムの重要性を改めて感じました。
第3回目の授業:異なるアプローチを組み合わせた、創造的な課題解決
翌週の2月14日に見学した授業では、生徒たちが考えた課題解決案の発表が行われていました。
グループごとに、「選んだ課題カード」「解決策(選んだ計測・制御カード)」「プログラミングのフローチャート」「新規性や実用性」を発表していました。
特に印象的だったのは、各グループがタコラッチを実際に作動させながら発表を行った場面です。各グループが選んだ制御方法は一つではなく、異なるアプローチを組み合わせて工夫しながら、自分たちなりの解決策を考えていました。
例えば、「寝たきりの高齢者がヘルプサインを出した時に家族に伝える仕組み」を考えたグループは次のように3つの制御を組み合わせて使用していました。
- 警報音を鳴らす
- 明かりを点滅させる
- (サーボモーターを利用して)ヘルプと書かれた旗を上げる
多くの場合、「警報」という目的を達するための方法として「音を鳴らす」ことを選択することが多いのではないでしょうか。しかし、生徒たちからは、「ライトを光らせる」という視覚的な解決策も提案されていました。
さらに、このグループは制御の種類の多さだけでなく、「1回では気づいてもらえない可能性があるから、ループさせよう!」と、伝えるための工夫をしていた点もとても印象的でした。
発表を通して、生徒たち自身がこれまでの生活のなかで感じている「気づきにくさ」が、今回の課題解決方法として生かされているのではないかと感じました。
課題に対する多様な視点と、「自分ごと」としての当事者意識の強さが生み出す解決策の解像度の高さ。そして、複数の方法を組み合わせて「伝える」工夫が自然に行えるのは、筑波大学附属聴覚特別支援学校の生徒たちの強みなのではないでしょうか。
“制限”は必要なかった――先生が見た生徒の可能性
今回授業を担当した技術科の福島先生は、当初、聴覚に障がいのある生徒たちに「音」を使って知らせるコードブロックの扱いについて悩んでいたそうです。生徒たちのきこえは様々であり、「音」の活用を避けた方がいいのか、それとも自由にコードブロックを使っていただくか、迷っていたとのことでした。
しかし、その迷いは杞憂に終わったようです。授業では生徒たちが本当に楽しみながら、音も含めた全てのコードブロックを使い、課題解決へ試行錯誤しながら取り組んでいました。授業を終えた先生は「教員が消極的になる必要はなかったのだ」と感じたそうです。
自分ごととして課題を捉え、より実用的な解決策を考えようとする姿
私たちが見学をする中で、担当の福島先生が用意した授業の提示資料が特に目を引きました。条件分岐やしきい値といった専門用語は、視覚的に理解しやすいように工夫されていました。
彼・彼女らが考える課題の捉え方には、自身の経験や課題意識が色濃く反映されており、「気づいてもらえない」「伝わりにくい」という日常の中で感じる問題をもとに、防災や安全対策のアイデアを発想していたことが印象的でした。
また、単一の解決策ではなく、「音+光+振動」といった複数の要素を組み合わせるなど、より確実に課題を解決する方法を模索する姿勢を見ることができました。これは、単に技術を学ぶのではなく、自分ごととして課題を捉え、より実用的な解決策を考えようとする意識の表れだと感じました。
このような学びの姿は、みんなのコードが提案する「小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデル案」と通じる部分が多いと感じました。生徒たちは、まさに「つくることで学ぶ」 という姿勢を体現していました。
今後も「アラムコSTEAMチャレンジ」を通じて、より多くの生徒が技術を活用しながら主体的に学ぶ機会を提供できるよう、取り組みを進めていきます。
今回ご支援いただいたアラムコ・アジア・ジャパン株式会社は、サウジアラビアの総合エネルギー・化学企業アラムコの日本法人です。
▶︎アラムコ・アジア・ジャパン:Where Energy is Opportunity | アラムコ・ジャパン ( https://japan.aramco.com/ )
▶︎アラムコ:Where energy is opportunity | Aramco
( aramco.com )