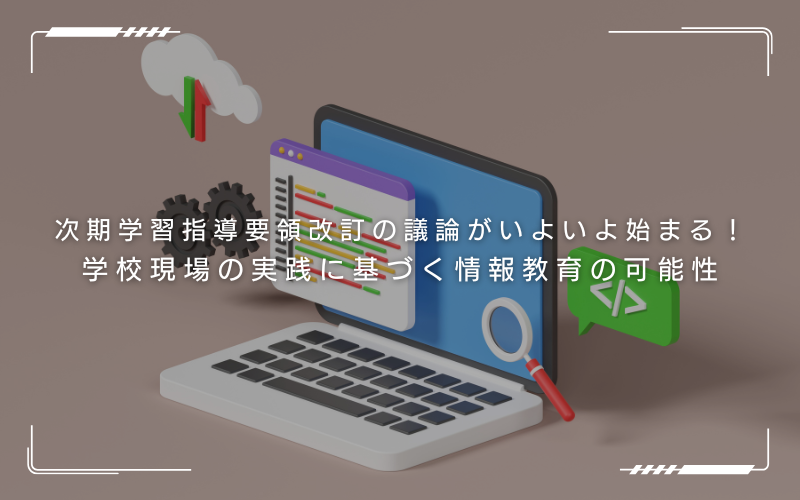みんなのコード代表の利根川です。
現在、文部科学省の中央教育審議会(通称:中教審)の教育課程企画特別部会で、次期学習指導要領の改訂に向けた議論が進んでいることをご存じでしょうか。
4月25日に開催される第6回会議から、「デジタル学習基盤を前提とした学びの考え方や情報活用能力育成の充実の在り方」の議論が始まる予定です。
情報活用能力育成の重要性については、これまで様々な観点から発信をしてきましたが、本格的に議論が始まるこのタイミングで、改めて私たちみんなのコードのこれまでの実践と考えを整理したいと思います。
情報教育の本質とは何か
学校教育の目的の一つは、子どもたちが「未来を生きる力」を身につけることだと思います。そして、その力は、時代とともに変化してきました。
現代社会に目を向けると、生成AIの台頭をはじめ、情報技術は目まぐるしく進化しています。情報技術は、生き方そのものをよくする手段として活用されるとともに、情報技術を適切に活用する力は、すべての社会人に求められる基本的なスキルになりつつあります。
昨年12月に公表された「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」でも、次のように言及されています。
生成 AI などデジタル技術の発展は、変化に伴う困難や負担を個人や社会に強いるだけではなく、多様な個人の思いや願い、意志を具現化し得るチャンスを生み出している側面もあります。生産年齢人口が急減する中、テクノロジーを含むあらゆる資源を総動員して、全ての子供が多様で豊かな可能性を開花できるようにすることが、我が国の未来のために不可欠です。
(略)
我が国のデジタル競争力は他国の後塵を拝しており、社会全体の生産性や創造性を高めていく観点からもデジタル人材育成の強化は喫緊の課題です。その一方で、実体験の格差やデジタル化の負の側面等を指摘する声もあります。「デジタルかリアルか」、「デジタルか紙か」といった二項対立に陥らず、「デジタルの力でリアルな学びを支える」との基本的な考えに立ち、バランス感覚を持って、積極的に取り組む必要があります。
「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について(諮問)」(2024.12.25)
こうした時代における「未来を生きる力」とは、課題を発見・解決したり、自分の思いや考えを表現・創造したりする力ではないでしょうか。そして、変化し続ける社会の中で、柔軟かつ積極的に情報を収集・判断し、活用し、新たな知見に向けた活動を可能にするためには、情報技術を適切に扱うことが前提条件となってきます。
情報技術との適切なつきあい方を体験的に理解することで、情報や情報技術を活用して新たな価値を創造できること、創造できるかもしれないと思えること。このような力を育成することこそが、情報教育の本質だと、私たちは考えています。
各学校での実証
私たちは前述の考え方のもと、これまで様々な学校とともに実証研究を積み重ねてきました。いくつかの取り組み概要と成果、共通して見えてきたことをご紹介します。
宮城教育大学附属小学校は、2018年度からプログラミング教育に着手し、20年度から宮城教育大学の安藤明伸教授(現・広島工業大学 教授)とみんなのコードとの共同研究でCS(コンピューターサイエンス)を新たな教科として実施する共同研究に取り組んできました。23年度からは文科省の研究開発学校の指定を受け、「小学校情報科」の研究を進めています。扱う内容を「コンピュータを活用した問題解決」、「情報技術の仕組み」、「情報社会とのかかわり」の3領域に整理し、情報や情報技術に対して、低学年では遊ぶ・気付く、中学年では使う・捉える・高学年では生かす・理解することを「目指す子どもの姿」として段階的に設定し、系統的な学びの在り方を研究しています。
6年生の「小学校情報科」では、6年間の集大成として、これまで学んだ情報技術などを活用し、身の回りの課題解決に取り組む「卒業制作」の単元があります。児童はプログラミング・AIなどを用いて、コンピュータの特性を生かした課題解決に試行錯誤しながら挑戦し、「画像認識AIを活用した出席確認システム」「楽しく漢字を学ぶことができるゲーム」などを制作しました。また、コンテンツを評価・改善しあう活動も通じて、これまでの学びが、どのような価値を生み出すことができるのか、実社会とどのように接続しているのかを実感することができていたと思います。
印西市立原山小学校では、2018年度から情報教育に力を入れ始めましたが、研究活動を通じてコンピュータサイエンス系のスキルを体系的に高めたいという課題が出てきたため、23年度は授業時数特例校、24年度からは教育課程特例校の指定を受けて、独自の教科「情報探究科」を設定して情報活用能力の育成に取り組んでいます。「情報とテクノロジーを巧みに活用し、創造的なアイデアを生み出し、多様性を尊重しながら積極的に持続可能な未来を築く」子どもの姿を目指し、学年ごとの情報活用能力体系表や他教科とのつながりも意識した情報教育カリキュラムを作成するなど、どのような活動を通じて、どのような力を育成したいのか、6年間を見通した情報教育を推進しています。
成果の一例として、FLL*での活躍が挙げられます。原山小では、23年度から情報探究科の中でFLLを題材にした活動を実施しており、大会にも参加しています。予選大会を突破し、小学4年~高校1年の全40チームが参加するFLL Challengeプログラムで、2年連続受賞・世界大会への進出を果たしました。民間のロボット教室や高校からの参加もある中、初出場の小学生が世界大会に進出することができたのは、プログラミングをはじめとする情報活用能力の積み上げがあったからではないでしょうか。
*STEAM教育と探究型学習を楽しく、実践的に学べる国際的な教育プログラム兼競技会。FIRST LEGO League。
日本女子大学附属中学校は、技術・家庭科 技術分野(以下、技術科)のカリキュラムを、より情報活用能力を高める魅力的なものに改善したいと考えていました。そこで、2023年にみんなのコードと「教科横断的な情報活用能力の育成に関する連携協定」を締結し、テクノロジー分野の教育の充実と、情報活用能力の育成を図るカリキュラム開発に取り組んでいます。1~3年の全ての学年で「D 情報の技術」の内容を扱い、情報技術による創造的・体系的な学びを通じて情報活用能力を育成することを目指しています。
技術科での学びは、他の教科ともつながっています。たとえば、技術科の授業で生成AIのしくみや適切な使い方を学んだ生徒たちが、社会科(公民)の授業で生成AIとディベートを行いながら、社会福祉について自分の意見を深めていく、という実践が見られました。このように、新しい技術を適切に学ぶことが、他教科の学びをより深める土台となっており、まさに学習の基盤としての情報活用能力が育成されていると言えるのではないでしょうか。
町田市立南成瀬中学校では、情報活用能力育成の中核である技術科の授業時数が少ないことを課題と捉えていました。技術科の授業は2週間に1回しかなく、前回の授業を思い出すだけで時間が過ぎてしまうこともあったとのことです。そこで、2024年度から授業時数特例校の指定を受け、3年生の技術・家庭科 技術分野の授業時数を、国語、社会、数学、理科、保健体育、英語から3時間ずつ拠出し、17.5時間から35時間に増やすとともに、授業内容や方法も見直し、情報活用能力の育成を強化する試みを行っています。
取り組みは始まったばかりですが、1週間に1回の授業の授業が安定的に実施できるようになったことで、管理職や担当の先生からは、「生徒から進んでプログラミングなどをやりたいという声が聞かれるようになった」、「進路選択の幅が広がったように思われる」など、ポジティブな声が挙げられました。
今年度は、「A材料と加工の技術」などでもデジタルものづくりの活動を取り入れるなど、「D 情報の技術」だけでなく、技術科の3年間を通じてさらに情報活用能力育成を推進していく予定です。
各学校の実践から見えてきたこと
この他にも様々な学校と実践を共にする中から見えてきたことは、継続的な積み重ねと、6年間・3年間を見通した計画の重要性です。
例えば、原山小の先生方は、「低学年から体験的な学習を始め、段階的にコンピュータサイエンス分野のスキルを身につけていくことが大切。6年間の実践を通してカリキュラムを改善し続ける必要がある」とおっしゃっていました。
どのような情報活用能力を児童・生徒に身につけてほしいのかを学校全体で考え、6年間・3年間をかけて体系的・継続的に情報活用能力を育成していこうという姿勢が、情報技術を用いて課題解決をしたり、価値を創造する児童・生徒の姿につながっているのだと思います。
考えてみれば当たり前で、高校の教科「情報」が始まって二十数年・情報活用能力が現行の学習指導要領で学習の基盤となる資質・能力と位置づけられてまだ5年なのに対して、他の百年超の歴史のある教科では、12年間の継続的な学習の積み上げが実施されています。また、その積み上げが頑健であることが日本の教育の強みであり、国際的にもPISAでTOPレベルになっています。
残された課題と次期学習指導要領への期待
ご紹介した学校の先生方は、いずれも取り組みに手応えを感じています。しかし、学校間の接続が次の課題であると考えています。
現在の学習指導要領改訂の議論では、前述の情報活用能力の議論に加えて、教育課程をより柔軟にする事がトピックになっています。学校間の接続の課題を考えると、教育課程の柔軟化と情報活用能力の育成という二つの議論を、良いバランスで両立させなければならないと考えています。
様々な学校が、頑健にカリキュラムが組まれた既存の各教科等を学校の実態に合わせて柔軟に編成できるようにすることは、基本的に良いことだと考えています。また、先程の事例のように柔軟化された教育課程編成の下で、情報教育に積極的に取り組んでいくことは素晴らしいことです。しかし、一校だけの取り組みには限界があります。同じ校区・地域でも学校の取り組みに差があり、一人ひとりの子どもの目線に立って考えると、進学先でスムーズな積み上げが始められないという姿もこれまで多く見てきました。
「情報」は他教科等に比べて歴史が浅く、情報活用能力の育成の取り組みは、まだまだ発展段階です。学校の創意工夫を活かすしくみはもちろん大切ですが、小中高の12年間を通じて情報活用能力をきちんと積み上げて育成するためには、各学校段階の卒業段階で目指したい姿は学習指導要領としてしっかりと示される必要があるのではないでしょうか。
またその際、情報活用能力の育成内容に、偏りが出ないようにすることも指摘したいと思います。2023年12月にまとめられた「情報活用能力に関する意見交流会における意見の整理」では、情報活用能力を育成するための学習内容として
- デジタル技術の適切な活用(基本的な操作、情報モラルの育成。生成AIの活用を含む。)
- デジタル技術を活用した課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現
- 情報科学、プログラミング・数理・データサイエンス・AI等
- 情報モラル等
に整理することが提案されています。このうち、1,2,4に比べると3に関連する実践はまだまだ進んでおらす、取り組みの優先度が低い学校も見受けられます。しかし、1〜4は密接に関連するものであり、未来を生きる力としての情報活用能力を身につけるためには、3のような要素も体験的に学ぶ必要があると考えます。
学校の自発的な取り組みに任せるだけでは差が広がり続け、体系的な情報活用能力育成が進まない可能性があることを踏まえ、1~4のいずれの観点でも学校間の差がなくなるよう、「未来を生きる力」の育成のために必要なことを、きちんと学習指導要領に位置付けることを望みます。
学習指導要領の議論は、まだ始まったばかりです。私たちは引き続き、実践事例について発信するとともに、様々な関係者と議論を深め、子どもたちにとってより良い学びが実現するよう、努めていきたいと思います。