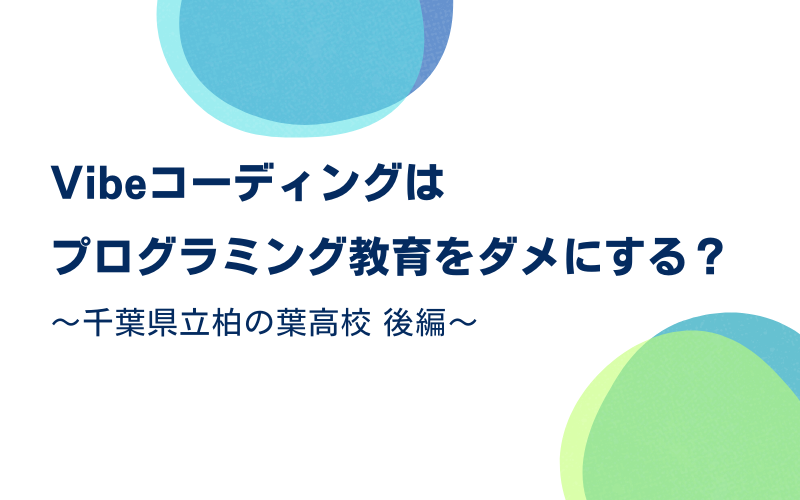こんにちは。みんなのコードの永野です。私は主に高校における生成AIやプログラミング教育の教員研修などを担当しています。
今回は、前回の記事の続編として、2025年7月11日に千葉県立柏の葉高校の1・2年生を対象に実施した「Vibeコーディング」の授業について考察します。
前編URL:https://code.or.jp/magazine/20250724/
「つくりたいもの」を「つくってみる」ことの価値
さて、1クラスにつき、たったの20分ずつの活動で、私は高校生の自由な発想による80個ほどのプログラムを目の当たりにした(https://code.or.jp/magazine/20250724/)わけですが、これをプログラミング教育の文脈からどう捉えるべきでしょうか。
現在プログラミング教育は、小・中・高を通じて行われており、2025年から大学入学共通テスト「情報」の出題分野にもなっています。
「生成AIにプログラムを書かせたら、プログラミング学習にならない」とか「プログラミングを学ぶ意義を見失うのではないか」との意見があるのも確かです。
一方で、今のプログラミング教育に大きな課題があるのもまた事実です。
生徒は「プログラミング」を学習する前は「アプリ作りたい!」「ゲーム作ってみたい!」という豊かな創作意欲を持っていることが多いです。しかし、プログラミングを学習するうちにだんだん苦痛になっていき、「さあ、一通り学習したから自由課題をつくってみよう」という段階になると、「もういやだ。二度とプログラミングなんてしたくない。」とすっかり嫌になってしまっている生徒を私自身、これまでに何度も目にしてきました。
プログラミングは単に「定期テストや大学入試に出るから学ぶ」のではありません。「テストの点を取る」より「つくりたい!」がプログラミング教育の根幹であるはずです。ただ、これまでのプログラミングは、知識やスキルを先に学ばなければ「つくること」ができなかったのです。
「つくるため」であったはずが、学ぶ過程で「つくりたくない」に変わってしまうのだとしたら、それは非常に不幸なことだと思うのです。
確かに、「生成AIにコードを書かせて終わり」にしてしまったら、プログラミング教育としては不十分かもしれません。しかし、Vibeコーディングは、「つくりながら学ぶ」ことによって自分の興味・関心を保ち、形にして動かす達成感を感じながら学ぶという可能性があるように思えるのです。
「つくれること」と「つくりたいもの」の関係
また、現在はプロのプログラマーも生成AIを使うことが当たり前になっています。むしろ生成AIを活用できないプログラマーは淘汰されていくことになってしまうでしょう。
「プログラミング」の世界そのものが、生成AIによってすでに大きく変化しているのであり、この事実を生徒に隠して旧来のやり方のみに固執するのは正しいことではない気がします。
これからのプログラミング教育が抱える最も大きな問題は、「誰もがつくれる」環境にありながら、生徒が「つくりたいものなんてない」「何をつくったらいいか先生が決めてほしい」となってしまうことです。生成AI時代の今だからこそ、「自分らしさ」や「アイデア」を尊重し、児童生徒の創造性や想像力を育てながらプログラミング教育を進めていくべきだと強く感じます。
授業の終わりに、以下のスライドを提示し、
- プログラミングは誰でも「楽しめる」ものになった
- 「つくりたいもの」があることの価値が跳ね上がる
- 自分が実現したいことを他者に伝えるためのツールにもなる
- まずは作ってみる「プロトタイピング」の重要性
- プログラムを実際に動かしながら、自分が実現したい知識やスキルを学べる
- 生成AIに任せっきりは危険。プログラム内のセキュリティやプライバシーは、今後も人が責任を持たなければならない。
- 知識やスキルは決して無駄にはならない。
といった話をして授業を終えました。
授業後、生徒たちからは
「楽しかった」
「生成AIってやっぱりすごい!」
などの声が聞かれました。
柏の葉高校での授業を通して、私自身Vibeコーディングの凄まじいパワーと、今後のプログラミング教育の可能性について大いに考えさせられ、また希望が湧いてくる授業となりました。
Vibeコーディングにご興味のある先生がいらっしゃいましたら、ぜひ「みんなのコード」永野までご連絡ください。
みんなのコードでは、プログラミングや生成AIを通じて、「誰もがテクノロジーを
創造的に楽しむ国にする」ことを目指し、今後も学校や先生方を支援する活動を続けていきます。