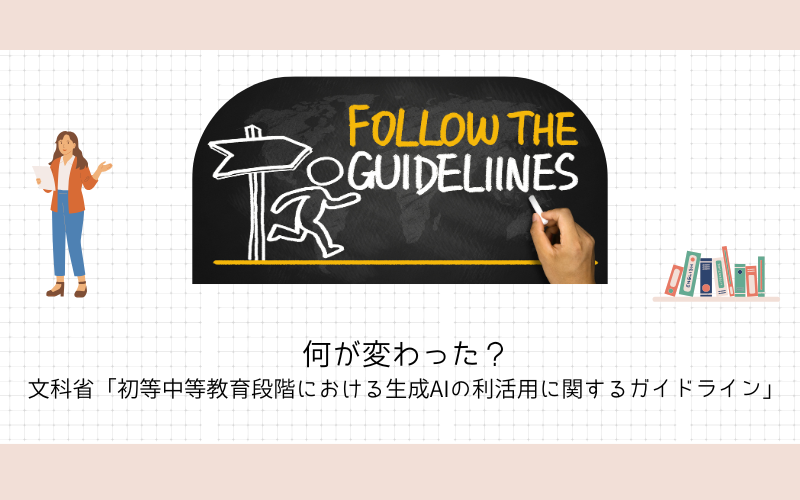みんなのコード、政策提言部/未来の学び探究部の田嶋です。
2024年12月に文部科学省から「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」(以下、Ver.2.0)が公表されました。これは、2023年7月の「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」(以下、暫定版)が改訂されたものです。
2023年に暫定版が公表された際、一次情報であるガイドラインガイドライン本体を読もう!というメッセージを込めて、「文科省『初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン』 〜自力で読みたい人のために、補助資料を今回も作ってみた〜」を書きました。
先日公表されたVer.2.0には、33ページのガイドライン本体を3ページのスライドにまとめた「概要資料」や、1ページのスライドにまとめた「概要1枚」が用意されています。そのほかにもガイドライン本文中に「読み手に寄り添ったものとなることを意識して改訂を行った」とあるように、場面や主体ごとのポイントがまとめられているなど、ガイドラインを読むハードルは全体的に下がったように思います。
そこで今回は、全体の解説ではなく「暫定版と比べて、Ver.2.0は何が変わったのか」をわかりやすくご紹介したいと思います。
原理原則の整理
1つ目の変更点は、生成AIを利活用するための原理原則を整理したという点です。
暫定版では、
個別の学習活動での活⽤の適否については、学習指導要領に⽰す資質・能⼒の育成を阻害しないか、教育活動の⽬的を達成する観点で効果的か否かで判断すべき。
とだけ記載され、あとは個別の「適切でないと考えられる例」「活⽤が考えられる例」の列挙にとどまっていました。
Ver.2.0では、「人間中心の原則を基本にしよう」「情報活用能力育成の観点から生成AIを考えよう」という二つの考え方が示されました。
人間中心の原則
「人間中心の原則」とは、「AI の利用は、憲法及び国際的な規範の保障する基本的人権を侵すものであってはならない。AI は、人々の能力を拡張し、多様な人々の多様な幸せの追求を可能とするために開発され、社会に展開され、活用されるべきである。」というものです。
この原則は学校現場でも同様であり、
- 生成AIと人間を対立的に捉えない、必要以上に不安に思わない
- 生成AIは、人間の能力を補助、拡張し、可能性を広げる道具になり得ると捉える
- 生成AIの出力結果は「参考の一つ」 、 最後は人間が判断する
ということを、生成AI利活用の原則とすることが言及されています。
情報活用能力育成
暫定版でも、
新たな情報技術であり、多くの社会⼈が⽣産性の向上に活⽤している⽣成AIが、どのような仕組みで動いているかという理解や、どのように学びに活かしていくかという視点、近い将来使 いこなすための⼒を意識的に育てていく姿勢は重要
との記載がありましたが、Ver.2.0では、
情報活用能力の育成に当たっては、生成AIが社会の中で果たす役割や影響、 生成AIに関する法・制度やマナー等について科学的な理解に裏打ちされた形で理解すること、問題の発見・解決等に向けて生成AIを適切かつ効果的に利活用し、情報社会に主体的に参画する態度を身に付けていくことが期待される。
と、生成AIに関して身につけたい資質・能力も、情報活用能力の3つの柱で整理された書きぶりとなりました。
場面・主体ごとのポイントを明確化
2つ目の変更点は、教員の校務利用、児童生徒の学習活動、教育委員会の3つに分けて、抑えるべきポイントが整理されたことです。チェックリストも校務利用・学習活動の二つの場面に分けられました。
特に、暫定版では言及のなかった、教育委員会が明確に読み手として設定され、先行事例の周知・研修実施・環境整備など、期待される役割が明確化されたことは大きな変化ではないでしょうか。
なお、利活用に当たってのポイントは、3つの主体に共通して、以下の5つに整理されています。
- 安全性を考慮した適正利用
- 情報セキュリティの確保
- 個人情報やプライバシー、著作権の保護
- 公平性の確保
- 透明性の確保、関係者への説明責任
1年半の進捗を反映
暫定版からVer.2.0までの間、生成AIの普及・技術の進展、議論・知見の蓄積が反映されていることが3つ目の変更点です。
生成AIの普及・技術の進展の観点では、児童生徒が、学校外で生成AIに触れていること、検索エンジンなどに組み込まれていることから意図しない形で生成AIを使う可能性があることや、ハルシネーションやバイアス再生成のリスクを軽減する技術が進展していることなどが言及されました。
議論・知見の蓄積については、ハルシネーションだけでなくバイアスの記述が充実したこと、「一度で求める出力がなされることを期待せず、複数回の対話の中で求める出力に近づけていく」といった良い使い方のポイントが加えられたこと、文科省の生成AIパイロット校での実践や研修動画など、参考資料が充実したことが挙げられます。
パイロット校以外への広がり
暫定版では、学校での生成AI利活用について、
- 限定的な利⽤から始めることが適切
- ⼀部の学校において(略)パイロット的な取組を進め、成果・課題を⼗分に検証
- (パイロット的な取組は)当面中学校以上で行うことが適当
という制限的な書きぶりがありましたが、これらの記述が全て削除されたことも特筆すべき変更点です。
なお、小学校段階の児童の直接利活用については、「発達の段階等を踏まえたより慎重に見極めが必要」と言及されている一方、「情報モラル教育やプログラミング教育の一環として教師による生成 AI との対話内容を数多く提示することなどを通じて基本的な事項を学んだり、生成 AI に関する体験を積み重ねることで生成 AI についての冷静な態度を養ったりしていくことが重要」ともされたことに注目したいと思います。
教師・学びの在り方にも言及
暫定版が公表された際にも「生成AIは学校教育が目指してきた姿を脅かすのではなく、むしろ後押しするきっかけになり得るもの」とご紹介しましたが、今回、この観点の記述の厚みが増したことを、5つめの変更点に挙げたいと思います。
具体的には、以下のように言及されています。
教育は、教師と児童生徒との人格的な触れ合いを通じて行われるものであり、適切な指導計画や学習環境の設定、丁寧な見取りと支援といった、学びの専門職としての教師の役割は、生成AIが社会インフラの一部となる時代において、より重要なものになる。
学習課題やテストの内容によっては、児童生徒が生成AIを用いることで簡単にこなせる可能性があることも前提に、(略)問題の本質を問うこと、深い意味理解を促すことを重視した授業づくりを行うことも期待される。
「概要資料」の概要版も作りました
ここまで、暫定版からの変更点を紹介してきましたが、この内容はあくまで「みんなのコードの目線で変化したと感じたこと」です。ぜひ、概要資料も活用しながら、ガイドライン本体もご一読いただきたいと思います。
とはいえ、このような行政資料を見ると「概要資料の概要が欲しい」と思われる方も、やはりいらっしゃると思います。
そこで今回も、ごくごく簡略化した資料を作成しましたので、ガイドラインを読み解く一助としてご活用いただければ幸いです。
▶︎ 【みんなのコード】文科省生成AIガイドラインVer.2.0 入門編
みんなのコードでは、「みんなで生成AIコース」の無償提供*や、生成AIに関する研修の実施等を通して、Ver.2.0が目指す生成AIの利活用が多くの学校で広がるよう、引き続き活動していきます。
2025年度も、引き続き全国の希望するすべての小中高で「みんなで生成AIコース」を無償でご利用いただけます。