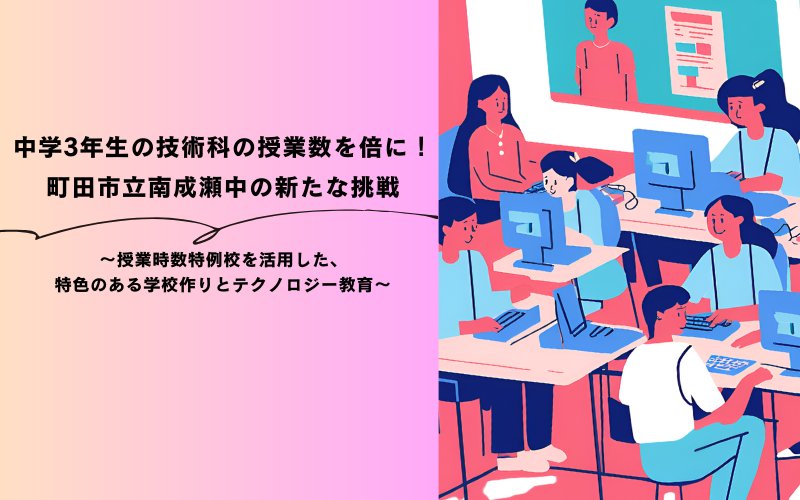〜授業時数特例校を活用した、特色のある学校作りとテクノロジー教育〜
みなさん、こんにちは!みんなのコードで中学校の担当をしている千石です。普段は、中学校の技術科向けの教材やカリキュラム開発、先生方への研修を行っています。実は私自身、東京都内の中学校で技術・家庭科(技術分野)の教員として11年間勤めていました。現場の経験を活かして、教育現場の変化や新しい取り組みをサポートしています。
みんなのコードが昨年から支援をしている、東京都にある町田市立南成瀬中学校(以下、南成瀬中)では、2024年度から新たな取り組みが始まりました。同校では、「授業時数特例校」*という仕組みを活用して、これまで17.5時間だった中学3年生の技術科の授業時数を35時間に増やす試みをスタートしています。この実践は、情報教育を強化したいという学校独自の目標に基づくものです。
一般的に中学校の技術・家庭科の授業時数は、1年生と2年生でそれぞれ70時間、3年生ではわずか35時間と定められています。そのうち技術分野に割り当てられるのはさらに半分の17.5時間です。この時間数では、2週間に1回程度の授業しか行えないため、十分な学習の機会が確保できない課題がありました。
南成瀬中は、学校独自の取り組みとして情報教育に力を入れたいと考えていたところ、みんなのコードの「教育課程・授業時数特例校制度で取り組む特色ある情報・テクノロジー教育事例について」を知り、2024年度から中学校3年生の技術科の時数を17.5時間から35時間に増やす実践を行うことになりました。
今回は、南成瀬中で技術科を教えている笠松先生にお話を伺いました。
*授業時数特例校制度とは
授業時数特例校制度とは、通常の学校よりも柔軟な授業時間数を設定できる制度です。この制度は各学校単位で申請することができ、地域の特性や生徒のニーズに応じた教育を提供できるようにすることを目的としています。具体的には、学習指導要領で定められた授業時間数を基準にしつつ、学校が独自に設定した教育目標に合わせて授業時間を調整することが可能です。
話し手:町田市立南成瀬中学校 技術科 笠松喜徳 主幹教諭(肩書きは2024年インタビュー当時)
聞き手:みんなのコード 講師・研究開発 千石一朗
授業時数特例校の取り組みについて
千石
本来であれば、3年生の技術科は隔週で授業をするところ、授業時数特例校制度を使うことで、週に1回授業を行っていますよね。率直な感想を教えてほしいです。
笠松先生
やってよかったというのが正直な感想です。時数が増える分、今までよりは確かに大変な部分はあります。しかし、その分子どもたちに教えられる内容が多くなるので、 自分も楽しかったし、良かったなっていうのはあります。
2023年度までは、中学3年生は2週間に1度の授業だったので、前回の授業を思い出すだけで時間が過ぎてしまう場合がありました。なので、率直な感想としては、教員の手間が増えることよりも、やってみてよかったな…と。
千石
子どもたちに学ばせたいことをしっかりと教えることができたという満足感ですね。
授業数が増えたことでの負担感についても伺えますか。南成瀬中は1年生4クラス、2年生5クラス、3年生4クラスの計13クラスで、都内では中規模校だと思うのですが、いかがでしたか?
笠松先生
私の持ち時間数の負担は、11時間/週から13時間/週へ2時間増えたのですが、これぐらいだとさほど負担感はなかったです。
これを6クラス×3学年=全18クラス規模の学校で同じように実施しようとすると、技術科の持ち時間が15時間/週から18時間/週に増えます。
そうなってくると、特例校の取り組みを、技術科の教員側が必ずしも「はい、やりましょう!」と簡単には引き受けられないと思います。3時間とはいえ絶対数が増えていくので…本校のように(全校規模が)12〜13クラスが限度のような気がします。
私は1〜3年生どの学年にも、毎時間生徒に対してレポートを課しているので、 正直言うと今の時数で一杯いっぱいです。これ以上時数が増えてしまうと、毎時間のレポートチェックが厳しくなるので、 規模的には本校のような13クラスくらいが限度かな…と。
レポート課題の間隔を、2週に1回というペースにすればまた少し違ってくるとは思うんですけど、そうすると次は評価の間隔が開くため、できれば今と変わらずできれば良いと思います。
千石
今回、技術科の時数を増やすにあたって、他の教科、国・数・社・理、 保健体育から授業時間数を供出してもらいましたよね。笠松先生は教務主任もなさっているので、時間割の組み立てが大変だったと思うのですが、いかがでしたか?
また他教科の先生方のご意見として、マイナス面とか、困りごとなどはありましたか?
笠松先生
各教科で時数が減ってしまって困った…といった意見は出ていません。ただ、週ごとに組み替えなきゃいけないので、 その部分でちょっと不規則※になるというところがマイナスだったかもしれません。ここはもう少し良い方法がないか検討しているところです。
とはいえ、全体では問題というよりは、授業数増により3年生が毎週技術科の授業ができるので、ちゃんと定着させるべきことを、丁寧にできるようになったので、プラスの面の方が多かったのかな…と思います。

<コラム>学校の時間割について
小学校と中学校では、時間割の作成方法に大きな違いがあります。小学校では学級担任制が基本となっており、授業の多くを担任の先生が担当します。そのため、自分の学級だけで他への影響が出なければ、比較的柔軟に入れ替えが可能です。
一方、中学校では教科担任制が採用されており、各教科を専門の先生が担当します。このため、先生の担当する曜日や時間が全校の時間割として組み込まれており、1つのクラスの授業を変更する場合でも、他のクラスや先生の予定を調整する必要があります。そのため、小学校のように頻繁に時間割全体を組み替えることはあまり行われません。
小学校 中学校 時間割の作成者 主に担任 主に教務主任 時間割更新の間隔 短い(数週間に1回程度) 長い(学期に1回程度) 時間割の影響範囲 クラス 学校全体 ※ある地域の例。時間割作成については地域・学校によって異なります。
AIとプログラミングを織り交ぜた学習
千石
1学期の内容は、プログラミングとAIを中心とした授業になりましたが、生徒たちは教科書に載ってないことを学習していたので、「これはなに?」と思う生徒もいたのではと思います。今回授業で実践してた内容は、中学3年生のレベル感としては、いかがでしたでしょうか?
笠松先生
みんなのコードさんから提供してもらった、授業スライドやWeb教材で授業を行い、生徒たちにはわかりやすく良かった思います。私自身授業をやっていて手応えがありました。
Code.orgのWeb教材を使った授業では、AIにデータを学習させて、魚とゴミを分別させましたが、教師あり学習のポイントとして、人間は魚の色に着目しているのに、AIはヒレなど他の場所も追いかけていた…といったことに上手く気づかなかった生徒もいました。生徒にとっては少し高度な内容だったかもしれませんが、キャラクターが親しみやすく、男女問わず一生懸命取り組んでくれました。
千石
この学習の後に、ScratchとTeachable Machineを使ってジャンケンゲームを作りました。カメラの前で生徒たちはジャンケンの手をかざしていますが、画像認識AIはその周辺の風景や生徒達の顔なども学習しているので、背景や人が変わってしまうと画像認識AIが正しくジャンケンの手を判断できなくなってしまいます。
背景画像もAIが学習していることを理解している生徒は、ジャンケンの手以外に何も映らないようにカメラの向きや人の立ち位置を工夫していましたね。
笠松先生
そうでしたね。そこは画像認識AIの肝となる部分なので、教員側の指導で補っていかなければいけない点だと思います。そのためには、教員もAIについて正しく理解する必要があると感じました。
指導の難しさや負担感について
千石
笠松先生は、教員もAIを知る必要性を感じているとおっしゃっていましたが、指導していて難しかったところはありますか?
笠松先生
やはり強化学習や機械学習といったところを生徒たちにどうわかってもらうか…が難しかったです。具体的な「これ」というものが目の前にある訳ではないですし、教科書にもAIの記述がありません。私もAIというものを勉強してきた訳ではないので…
千石
その気持ちは分かります。そのため私も、一方的に教え込まない授業設計を心がけました。今回の単元では、まずAIについて学習し、プログラミングを通じてAIを活用する活動を行いました。具体的な製品やサービスを例示しながら、強化学習や教師あり/なし学習を数学を使わずに指導するというコンセプトで計画しました。Web教材やプログラミングを活用して理解を深めてもらうことを目指しました。しかし、それでも生徒が「聞く時間」が多くなってしまったことが反省点でした。
また、生徒によってScratchの習熟度にも差があったので、指導のご苦労があったと思いますが、いかがでしたか?
笠松先生
生徒たちの差は確かにありました。 Scratchをやったことある、なしの差は確かに大きかったです。私もScratchはあまり詳しい方ではないので、お互いに辛かったのではないかと…。ただ、授業を重ねるごとに、生徒たちも理解したり教え合ったりして学習するようになっていました。
千石
今回の授業の中で、生徒たちにあまり負荷をかけないようにジャンケンゲームを題材にしました。ジャンケンであれば、みんなルールを知っていて、フローチャートやアクティビティ図に落とし込む場合もそれほど苦じゃないと思ったので。AIがグーの場合、人間がそれぞれグー、チョキ、パーの場合、引き分け、負け、勝ち…となることはすぐにわかりますよね。
プログラミング初学者がいることを前提に相談して、このテーマに決めさせてもらいました。このテーマ設定について、笠松先生のご意見はいかがでしたか?
笠松先生
Scratchで精一杯の生徒が、複雑なものを作ることになってしまうと、やはり拒否反応を示すと思うので、ちょうど良かったですね。
確かにScratchで横スクロールするシューティングみたいなものも作れるのも知っていますが、ゲームだからと言ってみんなが興味を示すという訳でもありません。それから、画像認識AIとセットで扱うゲームという点ではぴったりだったと思います。キー入力でキャラクターを動かすものではなく、カメラに写る画像でプレーするゲームを自分たちで作るという体験も生徒たちにとっては新鮮だったと思います。
総じて言えることは、これまでの3年生は2週間に1時間という少ない授業回数だったので、これまでは表面的なことを一方的に説明して終わってしまうことが多かったです。しかし毎週授業することにより、これだけ密に情報に関する授業ができたのは生徒たちに取ってはプラスだと思います。
今後の展望
千石
今回の実践では、生成AIの利用はほとんどありませんでした。今後生成AIを活用した授業を行う際には、キャラクターや音楽を生成させて、それをゲームに取り込むことができたらよいと思っています。今年度は初の取り組みでしたので、詰め込みすぎないように次回以降の宿題としました。
ただ、生成AIを使わなくても自分たちの声を録音したり、手拍子で効果音を作ってみたり生徒たちがそれぞれ工夫を凝らしていたのが印象的でした。また、フリー素材サイトからキャラクターや効果音を入手して利用していた生徒もいました。
このあたりは著作権の学習と相性が良さそうだと思いますが、著作権の学習はどうされていますか?
笠松先生
教科書や著作権情報センターの資料などを活用しながら指導していました。ただ、今後はこうした作品作りの中から、誰かのコンテンツを流用する、または自分のコンテンツを素材として提供するという活動を通して、著作権の学習が進むと良いと思います。
千石
確かに、我々大人も「著作権フリー」と言ってもどこまでがフリーなのかあまり考えず利用してしまっている部分もあるので、大切な点ですね。
また、生成AIが生成したものについても、タレントや声優さんの声などが簡単に使えるようになったり、作家の絵や写真が本人の許可を得ずにAIの学習に使われてしまっている現状もあるので、この分野はしっかり学習してく必要がありますね。
インタビューを終えて
技術科の時数を増やしたことについて、授業を担当された笠松先生からは、総じてポジティブなコメントをいただきました。ご本人もおっしゃっていたように中3で隔週の授業では、時間をかけて製作したり、深く考えさせることは困難です。
私自身も、教員時代から課題と感じていたこの点に焦点を当てることができて良かったです。
現行の学習指導要領(H29告示)では、技術科にそれまでなかった「D(2)ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツのプログラミングによる問題の解決」が追加されました。また「D(4)社会の発展と情報の技術」という、材料と加工、生物育成、エネルギー変換の内容を統合し問題解決を図る学習も加わり、ボリュームが増加しました。
昨今の生成AIなど、情報分野の内容も増加・高度化が進んでいる中で、中3の授業時間を増やすことで、深い学びと実践的な内容を実現できた一方、教員の負担や時間割の工夫が課題として浮き彫りになりました。
みんなのコードでは、2024年7月に小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデル案を発表していますが、その一端を今回、南成瀬中で実践できたことは非常に有意義でした。今後は、加工、生物育成、エネルギー変換と情報が結びついた学習を進めていきたいと思います。