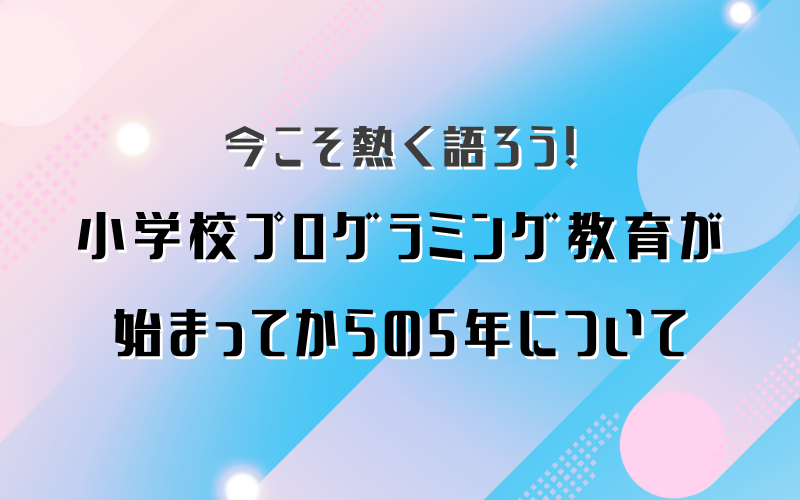小学校を中心とした研修・実証研究を担当している未来の学び探究部の竹谷です。
2025年1月19日に「小学校プログラミング教育必修化もうすぐ5周年フェス」を開催しました。参加者の皆さんのおかげでとても充実したイベントになりました。今回イベントレポートを会場の熱気の一端を2回に分けてお届けします。
今回のイベントで私は、みんなのコードに入社してからこれまでの8年間で多くの方々と出会ったことを改めて実感しました。そのつながりは、私にとってもみんなのコードにとってもたいへん貴重な財産となっています!

基調講演「これまでの歩みを振り返る」
まずイベントのはじめに私から、2016年に小学校プログラミング教育の導入が決まってから現在に至るまでのみんなのコードの取り組みについてお話ししました。
とりわけ「プログラミング指導教員養成塾」が大きく、2020年までの3年間で2,000人を超える先生方と研修や授業づくりを進めることができました。これはGoogleからの支援がなければできなかったことです。
ところが順調に進むかと思われた矢先にコロナ禍に見舞われ、残念ながら伸び悩んでしまいました。私見ですが、GIGAスクール構想による1人1台端末の環境が整ったものの、それを授業に取り入れていく方法の研修に重点が置かれたこともあり、プログラミング教育の定着は、一旦棚上げになった状態のまま現在に至ってしまっているのが現状ではないでしょうか。
しかし、全国の先生方の多様な実践は着実に蓄積されてきましたし、特定非営利活動法人タイプティーといった現役の先生による全国組織や東京都小学校プログラミング教育研究会といったネットワークが確立されたのも大きな成果です。
ご参加の皆さんで対話セッション
続いて、参加者の皆さんがグループでテーマごとに対話を深める「わいがや」のセッションに移りました。時間が来たことを告げてもなかなか区切りが付かないほど熱い話し合いとなりました。その中からいろいろなことが見えてきました。
自らつくり出していこうとする子どもたちの姿
印象的だったのは、「おもしろそう!」とか「もっとつくりたい!」と子どもたちが進んで取り組む姿が多く報告されたことです。授業で学んだことをきっかけに、自分たちで放課後や休み時間にプログラミングを続ける子が増えたことや、「友達とプログラミング教室を開こう!」と自主的に学びの場を作る子が現れたというエピソードが紹介されました。
「見て見て!」と成果を共有したくなる子、うまくいかなくても「もう一回やってみる!」と何度も試す子など、知識・技能や思考力といった側面よりも、子どもたちが学びに向かう力の高まりがうかがわれます。
また、「プログラミングが表現ツールになっている」という視点も興味深いポイントでした。従来の学習では表現が苦手だった子が、プログラミングを通じて「自分の思いを形にできる」喜びを感じている例が紹介されました。発表資料をスライドではなくスクラッチで作る子や、マインクラフトを活用して自分の世界を作り込む活動など、プログラミングが創造性を引き出す手段になっています。

可能性は広がるが課題も…
イベントを通して、多くの成果が見えましたが、プログラミング教育が十分に普及したかというと現場ではまだまだ課題も見られます。
まず、時間の確保を挙げた方が多くおられました。実施時数が定められているわけではなく、ただでさえ学習内容が多岐にわたる中で、どこに関連付けて設定するか悩むという声が聞かれました。
多くの先生が
「プログラミングをやらなければならないのは分かるが、具体的に何をすればいいのかが分からない」
「どの教材を選び、どんな手順で進めればよいのか」
と思い悩んでいるようです。
また、プログラミング全面実施から5年経つにもかかわらず、意義の理解が進んでいないのも大きな課題です。「プログラミングをやる意味が分からない」と感じている先生がいることで、結果的に積極的に取り組む先生とそうでない先生の間で「二極化」が進んでしまっているという指摘もありました。
このように、「子どもたちは意欲的なのに、環境や指導体制が追いついていない」という現状が浮かび上がってきました。
だから今こそ、そしてこれから!
GIGAスクール構想の実現が進み、基本的な利用については、子どもたちも先生も慣れてきた今、プログラミングを授業に取り入れる下地は整ってきています。
今こそ、改めていろいろなところからプログラミング教育の実践に取り組む流れをつくっていくことが必要です。このセッションを通して次のようなことに取り組んでいこうという声が上がってきました。
- 「楽しい!」や「できた!」という実感を得られる体験を重視する
- 自由に学び、自分の興味を表現できる環境づくりを心がける
- 先生たちが「何のためにやるのか」という意義について納得できるよう働きかける
- 支援体制の充実や教員研修によって自走可能な仕組みをつくる
- 校内でちょっとした実践を気軽に見合う機会を増やす
パネルディスカッション
イベント前半の最後には、当時「プログラミング指導教員養成塾」の講師を務めた福田(現 北区教育長)・松川・そして私が登壇。代表の利根川がファシリテーションとして参加し、パネルディスカッションを行いました。

福田からは、みんなのコードに参画する以前の養成塾1期生としての経験や、天沼小学校での利根川との出会いについて言及がありました。また、神戸市全小学校の校長研修を実施した経験から管理職が意義を理解することによって感じた手応えを語りました。自治体が管理職や指導主事の研修でビジョンを理解させることの意義について提言しました。
松川からは、加賀市で関わったmicro:bitを活用した課題解決の事例、さらには保育園での活動4年間にわたる関わりが紹介されました。継続的なカリキュラムによって体験を積み重ねていくことの重要性に触れました。
私は、教科横断的な学習や探究的な学習とプログラミングは相性がよく、まさに学習の基盤となる資質・能力を育む活動であるということについて、全国を回っての印象深い事例をいくつか挙げて語りました。
利根川からは、会場にきてくださった参加者の熱さに比べ、最近のプログラミング教育の足ぶみが見られる状況について、初期の普及が進んだ時期を振り返りながら言及がありました。
推進の気運が高まっていた時期には、先生同士が子どもの学びの姿を見ることで具体的な取り組みへの意欲を高めていく機会が多くあったが、コロナ禍を経てそうした機会が減ったままになっているのではないかという指摘です。改めて子どもたちの姿や育成を目指す力をみんなで共有しながら新たな歩みを進めていこうということで締めくくられました。
前半のまとめ
数多くの対話の中に、3つの共通したテーマが流れていることを感じました。
1つめは、子どもの姿をもとに語り合うことが推進のエネルギーになること、2つめはプログラミングを教科のための手段ではなく子どもたちの「つくりたい!」という意欲や「つくれそう!」という見通しを育てるためのものとする意義、そして3つめはそのためにビジョンを共有する環境や仕組みづくりです。
これからの新しい段階に向けて踏み出していくための手がかりが得られた時間となりました。