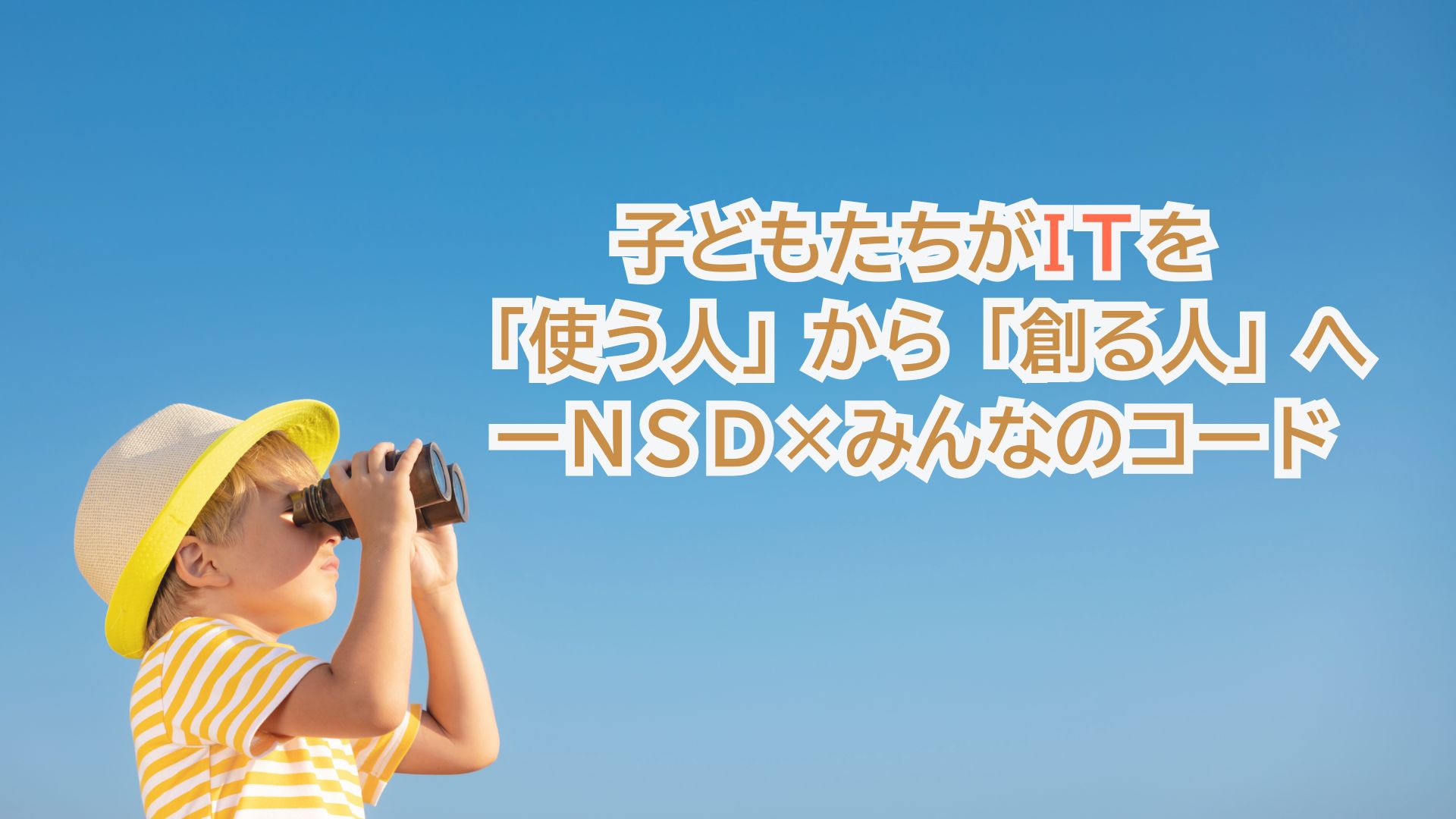みなさん、こんにちは。みんなのコード パートナー部の阪上です。私が所属するパートナー部では、みんなのコードの活動を応援してくださる企業・団体、個人の皆さまと、協業のご相談や寄付・助成のお願いなど、組織の内外をつなぐ役割を担っています。
今回は、私たちのパートナー企業である株式会社NSD(以下NSD)との協業事例についてご紹介します。
NSDは、東証プライム上場のIT企業です。同社は、「未来を担うIT人材の育成」を持続可能な社会への投資と捉え、社会貢献活動の一環として、教育分野におけるIT人材育成支援に力を入れていらっしゃいます。
NPO×企業が全国の教室に届ける情報教育支援
みんなのコードとNSDの連携が本格的に始まったのは2022年からでした。NSDの株主優待に「寄付」という選択肢があり、寄付先の1つとして、みんなのコードを選んでいただいたことからご縁が始まりました。いただいたご寄付は、子どもたちがテクノロジーに触れることができる環境整備に活用しています。具体的には、教材の提供、教員向けの研修、最新のテクノロジーを無償で体験できる居場所の運営や、子ども向けのイベントの実施などです。
さらに2023年と2024年には、「みんなで生成AIコース」の開発・改修・運用のための協賛もいただきました。ご支援いただいたおかげで、現行の学習指導要領にはまだ明確に位置づけられていない「生成AIの教育活用」というテーマを、いち早く、そして無償で全国の先生と児童・生徒に届けることができました。

2025年には全国の小中高教員向け研修に協賛いただいています。教材があっても、それを安全かつ効果的に活用する方法が学校現場に共有されなければ、実際に教室で使われることはありません。だからこそ、教材の次に、教員研修に引き続き協賛いただいていることは非常に重要で、心強く感じています。
学校の生成AI教育に取り組む理由
現在、学校現場では、生成AIを授業でどのように扱うべきか模索が続いています。背景には、2024年3月に文部科学省が公表した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関するガイドライン ver.2」があり、これを受けて全国で生成AIパイロット校制度の拡充や実証的な取り組みが進められています。
こうした動きに先駆けて、みんなのコードは2023年12月に、子どもたちが安全・安心に生成AIを学べる教材として「みんなで生成AIコース」を開発しました。2024年6月には全国の小中高校に向けて無償提供を正式にスタートし、あわせて全国の小中高教員向けの研修も展開しています。私たちは、現場の先生たちが「やってみよう」と思える教材や研修を通じて、生成AIの教育活用を後押ししたいと考えています。
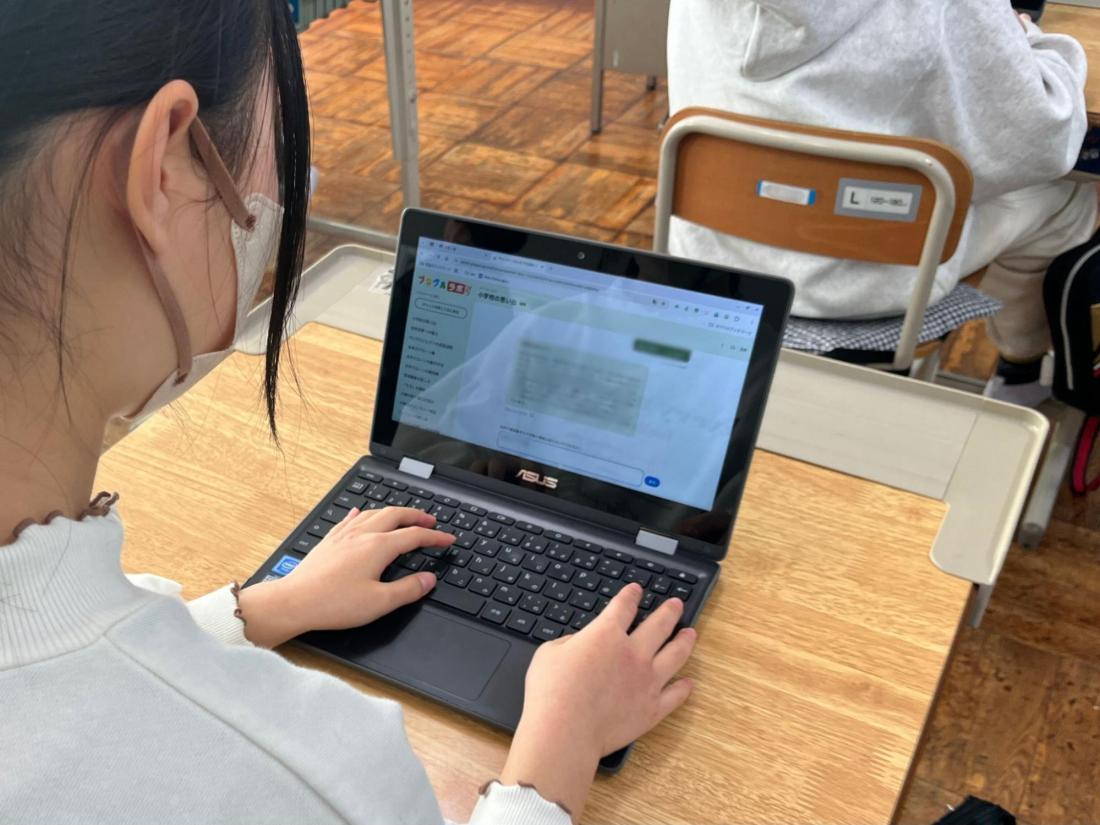
私たちが「みんなで生成AIコース」のような最新のテーマにいち早く着手してきた理由は、私たちのビジョン 「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」 にあります。
生成AIのような新しいテクノロジーは、子どもたちの「やってみたい」という気持ちを後押しし、その可能性を大きく広げてくれる存在です。
一方で、生成AIはすでに多くの子どもたちが学校外であたり前のように使い始めているにもかかわらず、授業での活用については学校や教員ごとに考え方に差があるのが現状です。このままでは、AIを活用した授業を受けられる子どもと、そうでない子どもとの間に大きなギャップが生まれてしまう恐れがあります。
そこで私たちは、この課題を解消するために、先生方が自信を持って生成AIのような新しいテクノロジーを授業で活用できるよう、研修や教材を通じてサポートしています。
そして、この想いに共感し、ともに取り組んでくださっている企業の一つが 株式会社NSDです。
学校現場で始まる生成AIの活用 〜 先生たちの気づきと挑戦〜
実際に、学校現場で「みんなで生成AIコース」を授業で活用している先生方の声や教員研修受講前後の先生方の声をご紹介します。
- やはり、これまでの学習観、というものを変えていく必要があると感じました。教師が一方的に知識を伝えるのではなく、子どもたちがあらゆる方法で知識を獲得していく、その環境を作り提供していかないといけませんね。
- 「みんなで生成AIコース」を活用したことで、導入期を円滑に進めることができました。「みんなで生成AIコース」は、まさに生成AIの導入期にぴったりなツールだと感じています。
- どうしても情報Ⅰ=プログラミングという先入観がありましたが、情報系科目に限らずすべての教科で求められる力であり、これからの社会を生きる生徒に不可欠な力であると認識できました。
ほかにも、生成AIの可能性と有用性を強く感じていらっしゃる様子で、「生徒にも体験させたい」「授業で活かしたい」という声が多数ありました。また、多くの先生が「まずは自分で使ってみて慣れたい」「もっと学びを深めたい」と、先生方自身がAIリテラシーを高めたいと思っていらっしゃるようです。さらに、学校全体での校内研修の実施や、AI活用を推進するための環境整備を求める声も見受けられました。
企業とつくる次世代の学び
情報教育は、2020年度に小学校でのプログラミング教育が必修化されて以来、中学校、高校へと段階的に拡充されてきました。こうした流れの中で、近年は生成AIのような新しいテクノロジーも、学校教育に取り入れる必要性が高まっています。
しかし、生成AIの教育活用はまだ始まったばかりです。現場の先生方は、どのように授業に組み込み、子どもたちに安全かつ効果的に活用させるかを試行錯誤している段階です。だからこそ、テクノロジーに強い企業の知見や継続的な支援は、教育現場にとって大きな後押しとなります。
最後に、NSD経営企画部 課長 今井潤さんのコメントをご紹介します。
弊社は、未来を担うIT人材育成に向けて、子どもたちを対象としたプログラミング教育や創造性を育むための活動を支援しています。プログラミング教育の多くは一方向ですが、「みんなで生成AIコース」等を使った学校の授業は「対話型」の双方向の学習で、子どもたちはより生成AIに親しむことができると思います。子どもたちが、ITを「使う人」から「創る人」へと成長していくこと、そして未来を創っていくことを期待しています。
情報教育は、常に「最新」が更新されていく領域です。そのスピードに私たちが対応し続けられているのは、NSDのように継続的に支援してくださる企業があるからです。
この記事を通じて、自社の事業活動の枠を越えて未来の教育づくりに真剣に取り組む企業の存在を、多くの方に知っていただけたら嬉しいです。