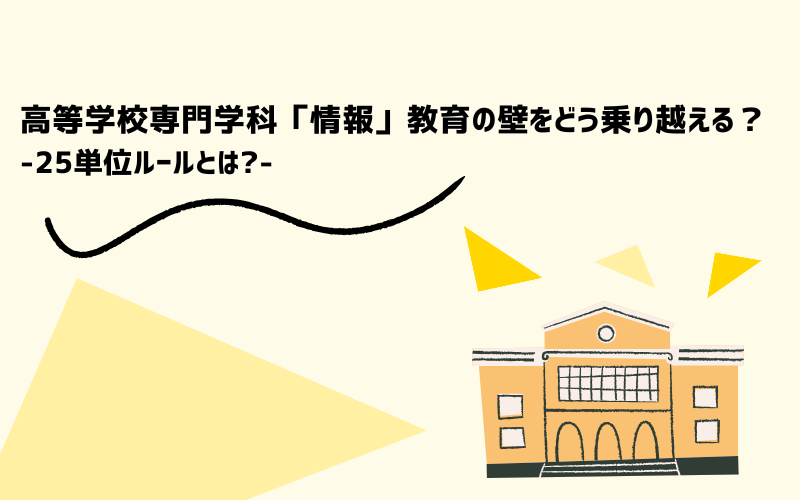こんにちは。みんなのコード永野です。私は主に高校「情報I」や生成AIに関する教員研修などを担当しています。
現行の学習指導要領によって、2022年より高校での「情報I」が必履修科目*1となり、すべての高校生は「プログラミング」や「データ活用」について学ぶ時代になりました。
しかし、生成AIをはじめとした「情報技術」の進歩は止まることがなく、これら次々に生まれる新たな「情報」関連分野について、学校教育はどのように対応していったら良いのでしょうか。
次期学習指導要領の改訂に向け、2030年代の「情報教育」について中央教育審議会の中で活発な議論が行われています。「何を学ぶか」について議論することも重要ですが、生徒たちの「学ぶ授業」がどのように決まるのか、いわゆる「教育課程」*2そのもののあり方も非常に重要です。
「教育課程」は、教育業界に関わる人でない限り、あまり詳しく知る機会はないのではないでしょうか。この記事では、教育課程における「情報」の現状について考えていきます。
*1必履修科目…各教科の中で、必ず授業を受けなければならない科目。国語は「現代の国語」及び「言語文化」、数学は「数学I」、情報は「情報I」など、各教科の必履修科目は学習指導要領で定められている。)
*2教育課程…「生徒がどの学年でどの科目を何単位学ぶか」を各学校で計画して決めること。
専門学科と「情報」の特殊な関係
教科「情報」は今から2世代前の学習指導要領(2003年)から新設され、当初から必履修となっていました。ただ、当時は「複数の科目から1つ以上の科目を必履修とする」という仕組みであったため、選択した科目によってはプログラミングやデータ活用を学ばないケースが多くありました。(画像参照)
実際、教科書の発行数から見ると、プログラミングやデータ活用を扱う「情報B」「情報の科学」を選択した生徒は全体の約2割にとどまっていました。
つまり、現行の「情報I」が始まる以前の世代では、プログラミングやデータ活用を学んでいた生徒はかなり少なかったのです。

2022年から年次進行で実施された現学習指導要領からは、プログラミングやデータ活用を含む「情報I」が必履修科目となりました。このことをもって「すべての高校生がプログラミングとデータ活用を学ぶ」ことになったと言われているわけです。
しかし、2022年以降も「情報I」を履修していない生徒は一定数存在します。
それは農業・工業・商業・家庭・水産・看護・福祉などのいわゆる「専門学科」で学ぶ生徒たちです。(専門学科には「情報」もありますが、こちらは当然のことながら情報の科目が充実しています。)
これら専門学科は「普通科」と異なり、「職業に関する各教科」を中心に学ぶこととされ、その職業に就くための専門的科目を学ぶ学科をいいます。かつては高校を卒業してその分野で働くための専門知識と技術を習得するための「職業教育」を行う学科という位置付けでしたが、いまは卒業後に大学や専門学校へ進学する生徒も多くなっています。
「情報I」は必履修なのに、専門学科の生徒たちは「情報」を学ばなくて良いの?という疑問がわくと思いますが、専門学科でも原則「情報I」は必履修です。しかし、学習指導要領には、
「専門教科・科目の履修によって,必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができる」
という定めがあります。
工業や商業では、機械の制御や仕事としてコンピュータに触れる機会も多いことから、歴史的にプログラミング等を含む「情報系」の授業が古くから実施されていたという経緯があります。このような事情で、「情報」が必履修となった2003年以降も、「専門教科の中で『情報』に準じた科目を履修していれば、「情報」を履修したこととして代替する(「読み替え」という)ことができるようになっているのです。
例えば、農業には「農業と情報」、工業には「工業情報数理」、商業には「情報処理」といった科目が「情報I」に準じた科目になり得るとして各専門学科の学習指導要領に例示されています。
情報技術の高度化と代替科目の現状
現行学習指導要領の「情報I」は学習内容が高度化し、情報による問題の発見と解決、プログラミング、データ活用、ネットワーク、情報デザイン、情報モラルとセキュリティ、情報関連法規など、かなり幅広い学習内容となっています。
本来、専門科目の「読み替え」は「同様の成果が期待できる場合」に限るとされており、代替する専門科目の目標や内容が「情報I」の目標や内容をカバーしているかどうかを慎重に検討しなければなりません。
しかし、各専門科目の代替科目は職業的な情報スキルの習得」が主目的となっていて、「『情報Ⅰ』の代替科目だけでは、情報活用能力を活用した問題発見と解決の指導が十分に行われていない状況」*3があるのではないか、と中央教育審議会 産業教育ワーキンググループで指摘されています。
私が関わらせていただいている商業科の高校の先生から、
「いわゆる「プログラミング検定試験への合格」が「情報」代替科目の学習目標となっていて、ひたすら過去問を解かせている。たとえ検定に合格したとしても、実際に生徒がプログラムを書くことはほとんどできない。また、大学入学共通テストを受ける生徒もいるのに、果たしてこのままでいいのだろうか・・」
という不安、ご相談をいただくこともあります。もちろん専門学科の中にも「情報I」の代替としてふさわしい授業が行われている学校もあります。
商業、工業高校は上記のようにプログラミングを扱ってはいるのですが、検定試験対策が中心となっていたり、他の専門学科の中には「情報I」で扱われるべき内容が十分とはいえず、ワープロ、表計算、プレゼンテーションソフトウェア等のいわゆる「ビジネス上のコンピュータスキル」習得が中心の授業を「情報I」の代替としてしていたりする学校も存在します。
現行の学習指導要領では、「情報I」の内容はすべての生徒に必要とされる学びと位置づけられています。大学入学共通テストにおいても、「情報」は志願先の学部を問わず原則必須とされました。
しかし、専門学科などではこれまでオフィスソフトウェアの操作に偏った授業を受けていた生徒も少なくありません。こうした生徒は、社会や各産業で求められる「情報活用能力」を授業の中で十分に獲得できないだけでなく、共通テストにおいても基礎的な出題にすら対応できないという大きな不利益を抱えることになります。
*3 https://www.mext.go.jp/content/20251007-mxt_koukou02-000045122_06.pdf
専門学科における「情報」の壁
では、専門学科で「情報」の内容をしっかり学ぶにはどうしたら良いでしょうか。
- 各専門科目の中で、「情報」の内容をすべて含んだ授業を行う
- 読み替えを行わず、教科「情報」を履修する
のいずれかで対応することが考えられます。
しかし、実現するには双方ともなかなか壁が高いのです。
1つ目の「専門科目の中で、『情報』の内容をすべて含んだ授業を行う」については、代替科目はそれぞれの専門教科の科目なので、それぞれの専門教科の先生が担当します。
工業や商業は「プログラミング」を主として担当する先生もいますが、「水産」「家庭」「看護」「福祉」などの学科では、「情報」の領域を専門としている先生はほとんどいないのが現状です。専門学科の中には、「高度化した『情報I』の内容をすべて含んだ授業を実施しろと言われても、担当者がおらず難しい」という状況にある学校はかなり多いと思われます。
もちろん必死に教材研究をして頑張っている先生方もいますが、現実的に見て、情報が専門ではない「水産」や「福祉」等の先生に「高度化した『情報I』」の指導(特にプログラミングやデータサイエンスの概念的理解)を求めるのは、酷ではないかというのも理解できます。
2つ目の「読み替えを行わず、教科「情報」を履修する」のはどうでしょうか。
これも実は指導要領上の規定に大きな壁が存在します。専門学科は「専門科目を卒業までに25単位以上履修しなければならない」という定めがあるのです。
この規定により、共通教科科目である「情報I」は専門科目の25単位の中に含めることはできず、専門教科の代替科目を「情報I」と単純に入れ替えることはできないのです。
専門学科においては、ただでさえ、国語や数学、外国語などの共通科目が少ないため、これらの時間をさらに2時間(「情報I」の標準単位数である2単位分)削減するのは難しいといえます。あるいは「情報I」を実施するために、週の授業時間を2時間増やすというのも生徒の負担がかなり大きいでしょう。
また、「情報I」を実施する場合には、「農業」や「工業」などの専門教科の免許ではなく、教科「情報」の免許を保有した先生が担当しなければなりません。
普通高校も「情報」の担当者を確保するのが難しいと言われている中で、専門学科を持つ学校に、新たに「情報」免許を保有する先生を配置するのはかなり難しいと言えるでしょう。
専門学科の「情報」はどうあるべきか
このように、専門学科が「情報」を履修するには数々の「壁」が存在します。しかしこれらはこれまでの教育システムや、教員不足といった社会状況から生じている問題です。
しかし、情報社会において、高校で学ぶ生徒たちにこれらの理由で「十分な学び」「自由な進路選択」が制限されるようなことがあっていいのでしょうか。
生成AIはあらゆる産業に関連し、農業(スマート農業)、工業(IoT)、商業(データマーケティング)、看護・福祉(医療DX / 介護ロボティクス)など、情報技術と無関係な専門分野はもはや存在しません。
工業科の中には「情報」の学びの充実のため、これら様々な「壁」を乗り越え、専門学科の25単位の履修を維持したうえで新たに「情報I」を教育課程に設定した学校もあります。同様の取り組みを進めようとする高校も今後増えていくでしょう。
次期学習指導要領においては、教員、生徒に過度の負担を強いることなく、すべての生徒が本来の「情報教育」が受けられる仕組みづくりが必要です。
この問題に対し、我々みんなのコードでは、2024年7月に「小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデル案」を公開しました。
この中で、高校においては
- 専門学科においても「情報I」を原則必履修科目とすべきではないか。
- 「情報I」に加え、学校の特色や生徒の状況に合わせ、「情報II」や「専門教科情報」の12科目からもう1科目を必履修にすべきではないか。
- この「情報」必履修2科目の単位数を、各専門教科25単位の中に含めることができるようにすべきではないか。
等の提言をしています。
こうすることで、「高度化した『情報I』の内容」を各専門教科の先生に押し付けることなく、「情報」の免許保有者が担当し、各産業に関わる「情報」の基礎的内容を専門学科でもきちんと扱うことができるようになります。
また、これらの「情報」科目を専門学科の25単位に計上できるようにすることで、授業時間数をいたずらに増やすことなく、情報の学びを充実させることができます。「工業」「商業」のみならず、「農業」や「水産」「看護」「福祉」においても、現代ではAIを含む「情報技術」は重要になり、各産業でも大いに役立つものと考えられ、各専門学科の単位数に「情報」科目をある程度含めることは、時代の流れにも合致しているはずです。
しかしながら、これらがもし実現したとしても、「情報」の担当者不足の問題は依然残ります。この方法だと、むしろ「情報」の担当者は今より必要になるわけです。また、教員のスキルアップや研修もより充実させていく必要があるでしょう。
「情報」の臨時免許状の授与、免許外指導の問題が明らかとなり、文部科学省によればこの問題は解消しつつある、とされています。しかし、初期に「情報」の免許を取得した先生方が定年退職を迎える時期となってきており、「情報」担当の先生方の採用を今後より一層増やしていく必要があります。
これは、大学の教員養成にも関わってくる問題ですが、なにより「教員志願者の不足」が根本的な問題でもあり、深刻な状況と言えます。
教員不足は高等学校「情報」に限らず、小・中・高・特別支援学校等、すべての学校に共通する問題です。子どもたちがこれからの社会で豊かに生きていくためにも、教員という仕事が、やりがいのある、価値ある仕事として社会に広く認識されなければならないでしょう。
専門学科は人々の生活を支える「産業」の発展を支える教育です。しかし、産業は「人」が支えているのであり、その「人」を育てるのは教育の使命です。DXを進めるべき農業や福祉など様々な産業の現場で、情報技術を効果的に活用する人材が不足してはならないでしょう。
人口減少が進むこれからの日本において、すべての産業で「情報技術」を学んだ若者たちが、AIを含む情報技術を活用し、より良い、より豊かな人間社会をつくっていく必要があります。そのためには、まずは人を育てる「教育」という仕事そのものを魅力的にしていくことが急務であるのではないでしょうか。
みんなのコードでは、2025・2026年度は「高等学校教員対象の生成AI研修」を無償で実施しています。生成AIの体験やこれからの学校の学びに生成AIをどのように活用していくべきか、などご希望に合わせて内容もアレンジします。各学校での実施やオンラインでの実施なども可能です。
みんなのコード永野まで、ぜひお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォーム:https://code.or.jp/contact-form/