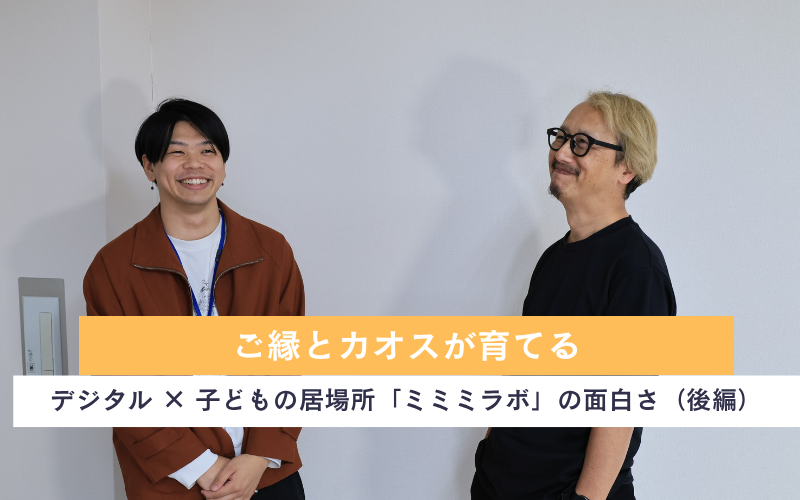こんにちは!ミミミラボ館長の溝渕です。
「ミミミラボ」は石川県金沢市にあります。2021年7月から三谷産業株式会社とみんなのコードが運営しているクリエイティブハブです。クリエイティブハブは、「デジタル × 子どもの居場所」をキーワードに、10代の子どもたちが気軽に、安全にテクノロジーに触れられる場です。
この記事では、ミミミラボの館長である溝渕と、コーディネーター・吉川による対談をお届けします。今回は後編です!今回は、拠点の企画づくりや私たちが目指すミミミラボとは?について話します。
前編URL:https://code.or.jp/magazine/20251105/
「ラボ」だからできる、新たなご縁と子どもへの機会
溝渕:
今、ミミミラボではいろんなプロジェクトが立ち上がったり、企画があったりするけど、一から私たちが考えたというよりは、何かの縁とか、ちょっとしたきっかけが繋がって生まれたプロジェクトが多いよね。
吉川:
特に去年ぐらいから私たちの施設をサポートしてくれている三谷産業から企画を振っていただくことが多いです。
例えば、三谷産業は昨年からプロ卓球チーム「金沢ポート」*のスポンサーになっていて、コラボイベントとして行う卓球教室に「ミミミラボも参加してほしい」と誘っていただきました。あと、情報システム事業部の方がAIプロダクトを作りたいから、その実証をミミミラボでやりたい!と声をかけてくださって、それがきっかけで新しい受付システムが開発されたりしました。

三谷産業がミミミラボをまさしく「ラボ」つまり実証の場として関わってくれることは、良い関係を築けている証拠だと感じています。
こうした様々な企画に誘っていただけることは、子どもたちを普段は体験することができない外の世界へ連れて行く機会にもなっています。例えば卓球のホーム戦に行くなんて、普通はないじゃないですか。そういう現場に声をかけていただき、子どもたちも一緒にいけるのは、ありがたいです。
あと、新しい企画について依頼された時、ストレートに返すのではなく「あ、ミミミラボに頼むと面白くなるな!」と思ってもらえるような一捻りを加えること、ここをすごく大事にしています。
溝渕:確かに。私たちが今までストレートに返したことはほとんどないな。何か一味つけて、今まであるような企画でもプラスアルファすることをやってきたので、年々味が出てる感じはすごくあるね。僕は関西出身だからかなんかオチをつけなきゃっていうのが身についてるのかも(笑)。
クリーンからカオスへ―変化を楽しむ居場所づくり―
溝渕:
ここからは、私たちがこれからミミミラボをどんな居場所にしたいかを話していきたいんだけど、結局、ミミミラボらしさって何かを考えると、1つは予測不能なとこがあるかな。利用者もそうだし、外部の方々も含め、いろんな人が様々な方向からボールを投げてくる。その時に、さっきも吉川くんが言っていたけど、ミミミラボに投げるとおもしろいよね!と思ってもらえたり、良くも悪くも想定外な方向に投げ返したりすること。そこに魅力を感じてもらっているのでは?と思っているんだよね。
吉川:
僕は、あえてミミミラボを一言で言うと「複雑さ」、あるいは「説明しづらさ」かなと思います。実際、そんな話をすることもあるのですが、クリエイティブハブという拠点が「デジタル」と「居場所」の両方の要素を持っているからこそ、説明が難しいと感じている人は多いと思っています。ただ、そのカオスが、ミミミラボの魅力なのかな、と個人的に感じています。
初期のミミミラボには、もう少し「クリーン」な印象がありました。社会的信頼を築くために立ち上げた時にとても大事なことだったと思います。それは、「子どもたちが安心して入りやすい場所づくり」を心がけていた前館長のおかげです。他にも前館長は、スタッフやメンターに向けて、海外ルーツの子どもたちやLGBTQについての研修なども精力的に行っていました。知識やリテラシー的な土台というか…僕もその土台は引き継いでいきたいなと考えています。
溝渕:
確かに前館長がやっていたことって、シンプルで分かりやすいことが多かった。だから周りの人たちも安心してミミミにやってきてたと思うな。今、吉川くんが言ってくれたようなことも、忙しくなると見過ごしがちだったり、きれいに整えられていなかったりするんだけど、本当にバランスよく土台を作ってくれたなって思うな。
どうしよう、わたしたち2人がちょっと壊していってる気もしないではないけど、まっそれもありかな(笑)。
吉川:
それも含めて「ミミミラボ」な気がします。人が増えたり、変わったりで多様な色が混ざり合って“カオス”になるのは必然だと思うんですよ。その変化を観察できること自体がコミュニティの魅力だと思いますし、「ミミミラボはこうです」と固定して進むのではなく、常に変化し続けながら居場所として存在している。そこが面白いところだと思います。
溝渕:
ああ、確かにそれある。いろんな人に聞いたら見え方はみんな違ってて。よく「結局何をしてるとこなの?」みたいなことを聞かれるんですけど、ほんまにいろんな側面があって、子どもたち、大人、アート界隈や教育関係から見るミミミラボ、それぞれ全部違うんだよね。だから答えにくいし、本当に変なとこだよなって僕も思います。
吉川:
これからのミミミラボがどんな人と繋がってどういう方向に向かっていくかは分からないですけど、これまでスタッフとして関わってきたみんな、ミミミラボがどう変わってもなんとなく変化を受け入れてくれるんじゃないかなと思うんです。あくまで僕の希望的観測です。
溝渕:
そうやな。私たち2人の色が変わって、施設の色も変わったとしても「あ、それもミミミラボだよね」って周りの人たちに思ってもらえたら嬉しいよね。
吉川:
個人的には、ほどよく無責任なことも大事な気がします。
“競争”より“共存”。金沢だからできる場のあり方
溝渕:
ちなみにミミミラボは、みんなのコードが運営しているクリエイティブハブの中でも少し異色で、他の拠点は人口の少ない自治体に位置していることが多いんだけど、中核市での拠点は今のところミミミラボだけだよね。クリエイティブハブとして中核市での新しい居場所のひとつの形を作っていっているような気がするな。
吉川:
クリエイティブハブの視点で見ると、ミミミラボは中核市における新しいモデルのひとつだと思います。ただ、金沢という街自体にはすでに子どもの居場所やシェアスペースなど、さまざまな場所が存在しています。
僕自身はミミミラボに関わる前から現代美術の領域で活動してきました。金沢には「オルタナティブスペース」と呼ばれる場所がいくつかあり、そこは作品をつくったり発表するだけでなく、人が集まって語り合ったり、たまり場のように過ごしたりできる、まさに「サードプレイス」として機能している場所がたくさんありました。
金沢の面白いところは、こうした居場所同士の関係がライバルではなく、ほどよい距離感でつながっていることかなと思います。たとえば同じ分野で活動する団体のイベントに呼んでいただいたり、これまでの僕のネットワークを通じてミミミラボが金沢の芸術創造財団の企画に参加させてもらったりと、それぞれの居場所同士の化学反応が生まれている気がします。
地域にある「居場所」が単に競い合うのではなく、ほどよい距離感でお互いに刺激を与え合える関係であることは非常に貴重なことだと思っています。子どもたちにとっても、さまざまな居場所があることで選択肢が増えるのは理想的で、地域全体で子どもたちを育てることにつながり、将来の可能性を広げていくはずです。こうした文化的な基盤そのものが金沢の魅力であり、中核市としての先進的な取り組みだと感じています。
溝渕:
あと、運営面ですごく助かっている部分としては、三谷産業がミミミラボの支援をするにあたって、短期的な成果よりも中長期的な価値を重視しているところだよね。やっぱり地域で100年近く続いてる企業である三谷産業の懐の広さ、すごさは日々感じるよね。

一般的に、民間企業が出資あるいは運営している施設って、何かしらの成果を測るためのKPIを設定したりするところが多いんだけど、三谷産業はそれが本当にない。この前、三谷社長とお会いしてお話しした時も「出資する目的って地域貢献ですか? 子どもたちが戻ってきて地域の産業を盛り上げてもらうためですか?」って聞いたら、「いや、そんなこと考えてないですね」って(笑)。「じゃあ金沢のためですか?」って聞いたら、「いや、金沢のためだけでもないし」っておっしゃってて。
もう石川とか日本とかに限らず、世界、いや地球規模でやってるのではないか、という感じで、三谷産業の考え方のすごさっていうのは、この会話からもすごく感じたかな。
吉川:
長い目で見てくださってることに対して、三谷産業の懐の深さを感じますよね。
そういう方々がミミミラボの活動を支えてくださっているのは心強く感じていますね。温かく見守ってくださっていることに感謝しています。
僕自身の理想としては、スタッフをはじめ大人が子どもたちを育てるのではなく、三谷産業と利用者の子どもたちと一緒に、ミミミラボそのものを育てていきたいと思っています。
ミミミラボ:https://mimimi-lab.jp/
みんなのクリエイティブハブ:https://code.or.jp/activity/hub/