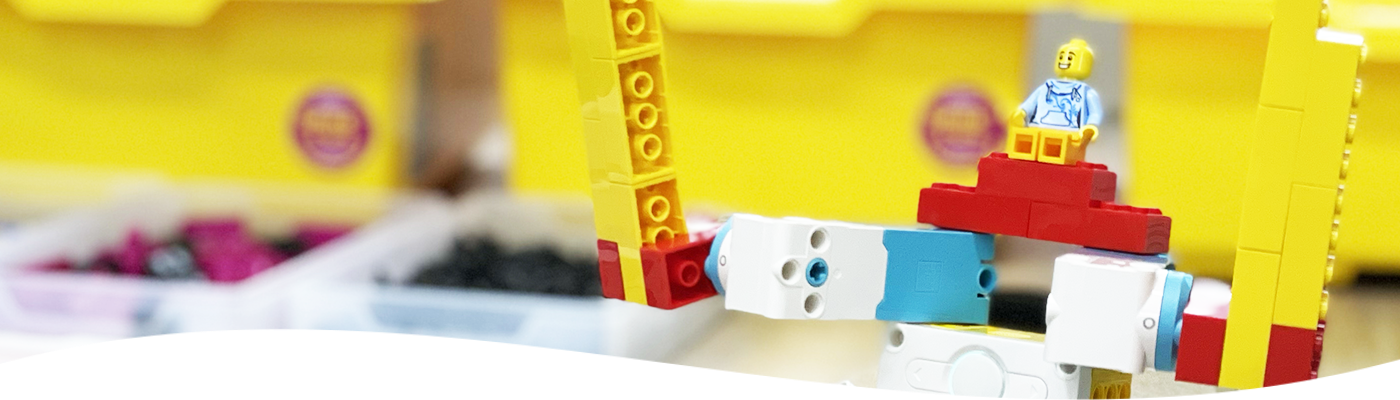特定非営利活動法人みんなのコード(神奈川県横浜市、代表理事:利根川裕太 以下みんなのコード)は、2025年7月に設立10周年を迎えます。
次の10年に向けて、私たちは、誰一人取り残されることなく、「みんな」が「未来を変える一歩」をテクノロジーと共に踏み出せる社会の実現を描きます。
当法人は、4月1日を夢を発信する日にしようとする「April Dream」に賛同しています。このプレスリリースは「みんなのコード」の夢です。
これまでの10年は「みんなの『コード』」
私たちの活動は、2015年に利根川が開催したプログラミングワークショップでの、子どもたちの生き生きとした姿から始まりました。テクノロジーを使って創作を楽しむ子どもの姿を全国に広げるため、この10年、みんなのコードは「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」をビジョンに掲げ活動してきました。
- プログラミング教育の普及
- 2020年の小学校でのプログラミング必修化を皮切りに、小中高の学習指導要領に準拠したカリキュラム・教材「プログル」の開発や全国での教員研修を実施。
- 学校外での学びの場の提供
- 経済的・地域的な事情に拠らず、子どもたちが無料でテクノロジーに触れられる第三の居場所「クリエイティブハブ」を運営。
- 生成AI時代の情報教育に関する提言
- 2030年代の学習指導要領の改訂議論に向けた政策提言及び実証研究を実施。とりわけ急速に進化するAI技術に対応した授業実践、教材開発やカリキュラムの提示を行う。
これらの取り組みを通じて、日本全国の子どもたちに、プログラミングを含むテクノロジー教育の機会を提供してきました。しかし、まだ私たちが解決しきれていない課題もあります。
次の10年は「『みんな』のコード」へ
私たちは、2023年にビジョンを「すべての子どもがプログラミングを楽しむ」から「誰もがテクノロジーを創造的に楽しむ国にする」に改定しました。
「誰もが」には、地域や家庭の経済状況、学校に通っているかどうか、性別や母語の違いなどに関わらず、すべての人を包摂するインクルーシブな取り組みを推進する中で得た気づきと思いを込めました。「テクノロジーを創造的に楽しむ」には、創業時から一貫して、子どもたちが単に消費者としてテクノロジーに触れるのではなく、自己表現や身近な課題解決、さらにはプログラミングを含むデジタル技術を使って価値を創造する姿を実現したいという願いを込めました。「国にする」には、条件が不利な地域や、社会から見落とされがちな子どもたちにこそ、機会がしっかりと届けられる仕組みを作りたいという私たちの強い意志を込めています。
テクノロジーは格差を広げる装置にもなりえますが、一人ひとりの可能性を広げる力を持っています。だからこそ私たちは、次の10年に向けて、私たちを含む「みんな」が「未来を変える一歩」をテクノロジーと共に踏み出せる社会の実現を描きます。
一人ひとりの「未来を変える一歩」がありたい社会を実現する
私たちが描く社会を実現するための原動力は、みんなのコードに関わるすべての方々と一緒に踏み出す「未来を変える一歩」です。私たちは、ひとりひとりの想いを共有しながら、ともに未来に向かって一歩を踏み出し、支え合える存在でありたい。そして、その輪を広げていきたいと考えています。
みんなのコード 代表理事 利根川 裕太
2022年のAprilDreamで私は、みんなのコードが「社会起業家が集まるNPO」になると宣言しました。一人ひとりのメンバーが、自ら気づいた社会課題の解決に主体的に取り組み、互いに支え合う組織を作りたいと願いました。
3年が経ち、私自身も新公益連盟をはじめ複数のNPOで理事を務める中で、社会的起業がこの国でもっと様々な領域へと広がり、その中から社会的インパクトを生み出す団体が数多く出てくる世界を作りたいという強い思いを抱いていることに気がつきました。
これは日本の資本主義の父といわれる渋沢栄一が500の企業に関わり、さらに100の社会事業の取り組みに携わったと言われる姿が私のロールモデルとなっています。
私は逆の比率で500の非営利、100の企業に携わりたいと考え、この国からたくさんの社会的起業が生まれるエコシステム作りに励むとともに、みんなのコードはその中のロールモデルの一つとなることを目指します。
みんなのコード COO 杉之原 明子
「みんなのコード」という社名にある「みんな」とは、一体誰のことを指すのか。果たして「みんな」に届いているのだろうか。
これは私たちが活動を進める中で向き合ってきた問いです。この問いを掘り下げるほど、地域や経済状況、性別や言語、教育環境など、さまざまな観点から論点が浮かび上がり、私自身もその難しさを感じてきました。
そして改めて気づいたことがあります。みんなのコードのビジョンは、決して一人や一つの団体の力だけでは実現できないということです。異なる思いや強みを持つ多様な人々とともに、誰もがテクノロジーを創造的に楽しめる未来をつくりたい。そのために、これからの10年は、これまで以上に広く、多様な領域の皆さまに関わっていただけるような仕組みをつくり育てます。
みんなのコードで働くメンバーの夢の一部
■子どもたちが住んでいる場所や環境に関係なく、ものづくりやプログラミングで社会を変えられる、そんな力を身につけられる学校を増やしたい。そのために、もっと若い先生やいろいろな地域の先生と交流して仲間を増やして行きたいです。(千石一朗)
■情報教育を通じて次世代の育成に貢献し、日本を再び幸福感に包まれた豊かな国にしたい。(K.H)
■ものづくりの楽しさを自分自身も実感しながら、子どもたちの可能性をもっともっと広げる活動がしたい。(Y.N)
■人間とテクノロジーの心地よい距離感と創造的で文化的な体験の創出。(Y.A)
■子どもたちが好きなことに挑戦し、自分らしく生きられるように。(N.S)
■楽しいことが一番伸びる、熱中している人が一番強い。そんな教育ができたらいい。(N.N)
■子どもたちが未来に希望と無限の可能性をもてるように、大人が輝き続ける姿をみせたい。(M.T)
■ソーシャルセクターこそ発信力が大切だとみんなのコードに入って知った。だからこそ、社会課題を広報の力で解決できる、ソーシャル界隈の広報マスタになりたい。(Y.Y)
■まずは自分の子どもに寄り添いながら、仕事を通じて、子どもたちの未来への希望や可能性が広がる環境づくりに貢献したい。今は子育てを理由に、自分の興味関心ややりたいことに制限をかけてしまっているけれど、自分がのびのびと活動し、新しいことに挑戦する姿を子どもに見せることで、ロールモデルの一つになりたい。(A.H.)
■子どもも大人も、故郷や好きな場所でそれぞれのキャリアを築けるように。(牛島青)
■30歳を迎える頃には、電気・水等のオフグリッド化、米・野菜類の農作物の自作などにより、物流・インフラへの依存率を下げたい。(Y.S.)
■子どもたちが得意なブリコラージュを日本に広げること。エンジニアリングばかりではなく、感性・直感を使って、今あるものを見つめる大切さを伝えたい。(ふるおかしほ)
■社会の中で働きながら作家活動を続ける現在、「制作を続けること」の困難さを強く感じています。形が変化したとしても制作活動を続けたいです。文化的に生活が出来、自由に制作に臨むことのできる社会であること、自分の意欲が途切れないことを願います。(吉川永祐)
特定非営利活動法人みんなのコードについて
みんなのコードは、全国でテクノロジー教育の普及活動を推進する非営利法人です。公教育におけるテクノロジー教育拡充に向けた政策提言や学術機関と連携した実証研究、授業用プログラミング教材の開発・無償提供、プログラミング教育を担う先生方向けの各種研修の企画・開催、子どもたちが自由にテクノロジーに触れられる第三の居場所「みんなのクリエイティブハブ」の運営など、幅広い取り組みを行っています。
代表理事 :利根川 裕太
設立 :2015年7月
コーポレートサイト:https://code.or.jp/
「April Dream」は、4月1日に企業・NPO法人がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。