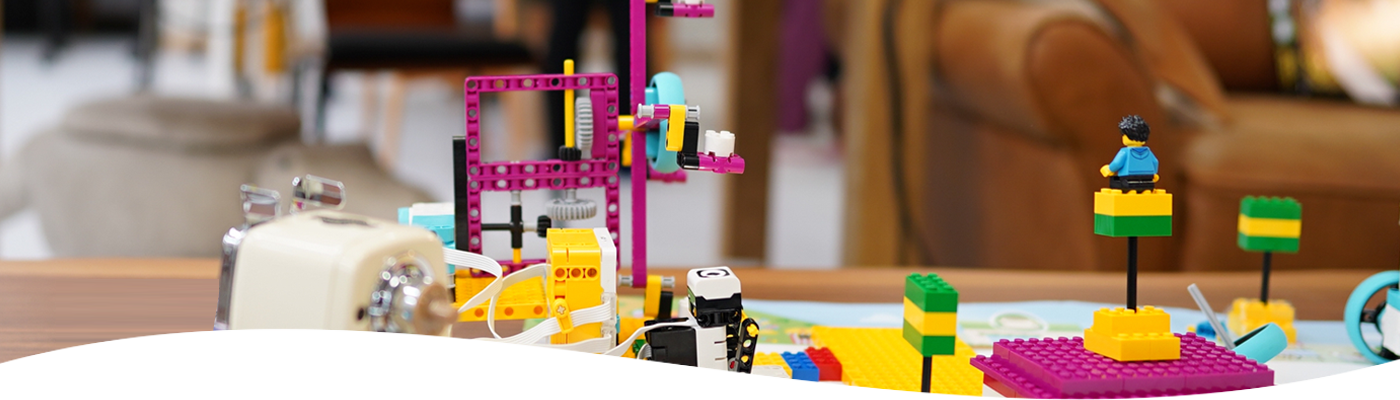Outline
団体概要
| 法人名 | 特定非営利活動法人みんなのコード |
| 設立 | 2015年7月 |
| 代表理事 | 杉之原 明子 |
| 拠点 | 横浜オフィス(神奈川県横浜市) ミミミラボ(石川県金沢市) てくテックすさき(高知県須崎市) |
| 主たる事務所 | 〒221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町7-3 金港ビル7階 |
| 従業員数 | 38名(全従業員に占める女性の割合 52.6%) |
History
みんなのコードのあゆみ
| みんなのコード | 社会ニュース | |
| 2015年 |
|
|
| 2016年 |
|
|
| 2017年 |
|
|
| 2018年 |
|
|
| 2019年 |
|
|
| 2020年 |
|
|
| 2021年 |
|
|
| 2022年 |
|
|
| 2023年 |
|
|
2024年 |
|
|
Governance
ガバナンス
経営チーム

利根川裕太 理事会長
2009年にラクスル株式会社の立ち上げから参画し、プログラミングを学び始める。2015年 一般社団法人みんなのコード設立 (2017年よりNPO法人化)し、全国の学校でのテクノロジー教育の普及を推進。2016年 文部科学省「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議」委員、 2024年横浜美術大学客員教授に就任、文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関する検討会議」委員。2025年より中央教育審議会初等中等教育分科会「デジタル学習基盤特別委員会」委員。

杉之原明子 代表理事
2008年に株式会社ガイアックス入社後、学校向け新規事業の立ち上げ及び責任者を経て、2014年アディッシュ株式会社設立及び取締役に就任。管理本部の構築及び上場準備の旗振りを行い、2020年3月東証マザーズ上場。2021年にみんなのコードCOO就任。ダイバーシティ経営をキーワードに、複数のベンチャー上場企業役員を兼任。

安藤祐介 CTO
在学中よりウェブサイト制作、起業準備に携わり独立。フリーランスとして多数のウェブシステム開発に携わる。その後、楽天株式会社などの国内外の様々なIT企業にてソフトウェア開発に携わる。2015年、Facebook (現 Meta) 入社。アジアとヨーロッパ、9カ国からなる多様なエンジニアチームを統括。2023年より現職。ビジネスブレイクスルー大学 経営学部 准教授、清泉女子大学 特任准教授を兼任。

市川衛 理事
武蔵大学社会学部メディア社会学科 准教授。医療の「翻訳家」。2000年東京大学医学部卒業後にNHK入局。医療・健康分野をメインに世界各地で取材を行う。16年スタンフォード大学客員研究員を期に(一社)メディカルジャーナリズム勉強会を立ち上げ代表に就任。20年より広島大学医学部客員准教授。25年より現職。主な作品にNHKスペシャル「睡眠負債が危ない」。

太田直樹 理事
New Stories代表。一般社団法人 コード・フォー・ジャパン理事。ボストンコンサルティンググループにて情報通信企業を中心にプロジェクトを推進。テクノロジーグループのアジア統括も務める。その後、2015年に総務大臣補佐官に就任し、IoT、AI、ビッグデータの政策を立案。現在は、コミュニティ主導のまちづくりや地域に開かれた教育など地方の仕組み作りを支援。

忍岡真理恵 理事
HERALBONY EUROPE 代表取締役 / CEO。2009年経済産業省入省、留学を経てマッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社で事業戦略などに携わる。その後、株式会社マネーフォワードにて事業開発、社長室長、IR責任者を務める傍ら同社のESGやダイバーシティ活動を推進。2023年ヘラルボニー参画。米国ペンシルベニア大学ウォートン校MBA(経営学修士)修了。2024年9月より現職。

宮島衣瑛 理事
広島大学大学院 人間社会科学研究科 特命助教。「テクノロジーを基盤とした未来のための教育をデザインする」をモットーに、全国で実践・研究を行う教育研究者。2015年に株式会社Innovation Powerを設立し、代表取締役社長兼CEOを務める。一般社団法人CoderDojo Japan理事や文部科学省委員、各種教育関連委員を歴任し、社会的活動も精力的に行う。2025年4月から広島大学大学院に着任。

寳角淳 監事
株式会社ストリーム代表取締役副社長。公認会計士・税理士。有限責任監査法人トーマツ、独立系コンサルティング会社を経て2010年に独立。上場会社及び上場準備会社の支援経験を生かし、各種コンサルティング業務を実施している。 また、上場会社の役員を務める等、財務会計に関する豊富な経験を有する。
組織図

Achievement
実績
委員経歴
| 2025年- | 中央教育審議会 初等中等教育分科会 デジタル学習基盤特別委員会 委員 |
| 2024年 | 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関する検討会議」委員 |
| 2023年 | 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」有識者 |
| 2021年 | 経済産業省「デジタル関連部活支援の在り方に関する検討会」委員 |
| 2018年 | 内閣官房「教育再生実行会議技術革新ワーキンググループ」委員 |
| 2016年 | 文部科学省「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議」委員 |
受賞歴
| 2024年 | 第7回リカジョ育成賞「奨励賞」を受賞 【受賞した取組】 情報教育をインクルーシブに〜女子中学校と取り組む、教科横断的な情報活用能力の育成〜 |
| 2023年 | 第6回リカジョ育成賞「奨励賞」を受賞 【受賞した取組】 小学校の女性教員向けに特化したプログラミング教育の教員養成プログラム「SteP」 |
| 2022年 | 「BIG LOVE ACTION powered by MINI」にて、第1期 Winnerに選出 【受賞した取組】 公共交通手段のないエリアの子どもたちに向けて「MINIで無料送迎サービス」 |
| 2021年 | 第7回企業ボランティア・アワード「大賞」を受賞 【受賞した取組】 株式会社セールスフォース・ドットコム 社会貢献委員会STEM教育チーム〔コンピュータクラブハウス加賀〕 SAPジャパン株式会社〔NPO法人 みんなのコード〕 Business Insider Japan「Beyond Sustainability 2021」Next Coming部門にノミネート リモートワーク × 健康AWARD「大賞」を受賞 |
学会一覧
| 2025年5月27日 | 人工知能学会 高等学校プログラミング学習教材へのGPT-4oによるアシスタントの導入 |
| 2025年3月16日 | 日本産業技術教育学会 情報分科会 授業時数特例校制度を活用した授業時数の増加がもたらす影響について |
| 2025年3月13日 | 情報処理学会 「高等学校プログラミング学習教材への生成AIの導入と効果」 |
| 2025年3月8日 | 日本教育工学会 小・中・高等学校における情報教育の体系的な学習を目指したカリキュラムモデルの提案 |
| 2025年2月28日 | HAIシンポジウム 学校向け生成AI教材の対話履歴からみる生徒の生成AI対話傾向の分析 |
| 2025年2月16日 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 小学校におけるコンピュータサイエンス教材の開発と授業実践 |
| 2024年 10月25日・26日 | 日本教育工学協会 女子中学校の技術・家庭科技術分野における情報教育の実践 ~ジェンダーの視点を踏まえた日本女子大学附属中学校での事例~ |
| 2024年 10月25日・26日 | 日本教育工学協会 <学びの作品化>を促す学習環境デザインの検討 ―表現方法の多様さが保障された授業に着目して― |
| 2024年 10月25日・26日 | 日本教育工学協会 対話型生成 AI が小学生の学習に及ぼす影響:特性の理解と活用の可能性 |
| 2024年 9月7日・8日 | 日本教育工学会 「生成AI100校プロジェクト」から見る生成AI利用の姿 |
| 2024年 8月17日・18日 | 日本産業技術教育学会 「情報の技術におけるAIを学習するカリキュラム開発と実践 |
| 2023年 10月27日・28日 | 日本教育工学協会 「学びの表現手段としてのプログラミング教育の探究ー「学びの作品化」の提案ー」 |
| 2023年 9月16日・17日 | 日本教育工学会 「「情報I」の授業に係る全国実態調査の実施とその概要」 |
| 2023年 8月24日 | 日本教育学会 「生成AIと子どもの対話関係についての研究」 |
| 2023年 8月20日 | 日本産業技術教育学会 「画像認識AIを活用した枝豆選別機の授業実践」 |
| 2023年 4月3日 | 日本産業技術教育学会 「クライアント・サーバを模したモデルによるチャットシステムの問題解決のための教材開発と実践」 |